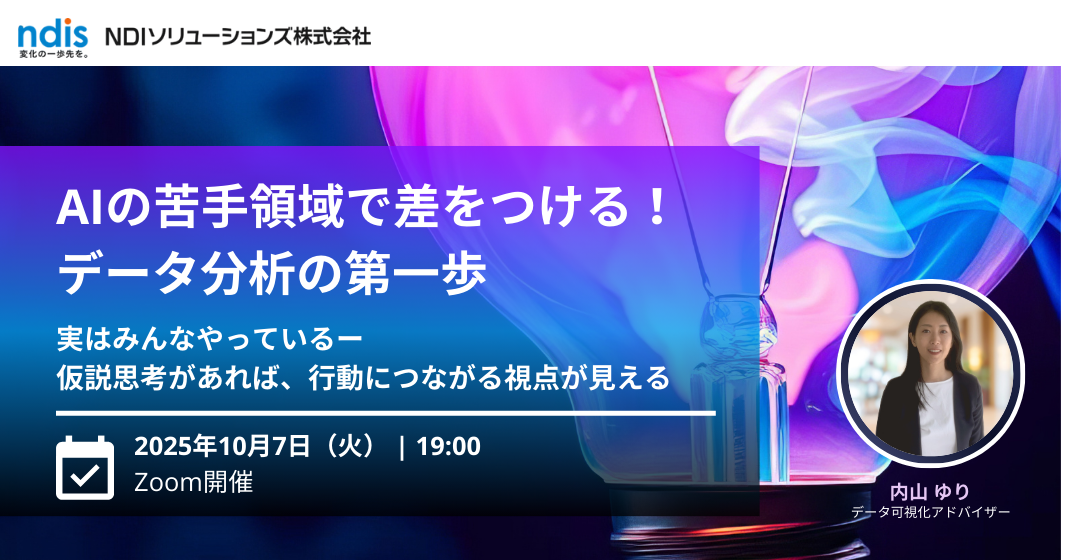ワーク・ライフ・バランス充実化の最前線|BIデータ活用とは
2025年03月18日 07:30

ワーク・ライフ・バランスとは、仕事と私生活の調和を図ることで、個人の幸福度を充実させ、仕事の生産性を向上させることを目的としています。しかし、この「バランスの充実化」を実現するためには、単に労働時間を短縮するだけではなく、働き方そのものを見直す必要があります。
本記事では、「ワーク・ライフ・バランス充実化」の一つの解決策として、近年ビジネスの現場でますます重要性を増しているBIツール(Business Intelligenceツール)を活用した方法をご紹介します。これまでの「ワーク・ライフ・バランス充実化」を目標とした企業が実施する施策は、一般的に浸透してきている一方で、それ以上の改善策や自社独自の課題にアプローチしようとしている企業は、まだ少ない状況です。記事内では、ワーク・ライフ・バランスの充実化の新たなアプローチ方法を実例と合わせて解説しますので、ぜひ最後までご一読ください。
ワーク・ライフ・バランスとは
『ワーク・ライフ・バランス』という言葉はよく聞く一方、実際にどんな定義でその言葉が使われているのかご存知ですか?また、最近では似たような単語も耳にする機会が多いことでしょう。この章では、まずはそれぞれの言葉の意味について理解を深めていきます。
ワーク・ライフ・バランスの定義
ワーク・ライフ・バランスとは、個人が職業生活と家庭生活の両方を充実させ、心身の健康を保ちながら、社会的な役割を果たすことを指します。この概念は、仕事とプライベートの時間やエネルギーの配分を適切に調整し、どちらにも偏らない状態を目指すものです。従来の働き方では、長時間労働が当たり前とされ、家族との時間や個人の成長に必要な時間が犠牲になる場面が少なくありませんでした。しかし、ワーク・ライフ・バランスの考え方は、働く人々がより豊かで満足度の高い人生を送るために、仕事の効率化や柔軟な働き方を促進するのを目的とこの考え方が定着しつつあります。具体的には、フレックスタイム制度やリモートワーク、育児休暇の充実などが、ワーク・ライフ・バランスを実現するための手段として挙げられます。特に日本のような長時間労働が常態化している国々において、労働環境の改善や少子高齢化対策としても重要視されています。
ワーク・ライフ・バランスを適切に実現することで、従業員の生産性向上や企業の持続可能な発展にも寄与するため、企業と個人の双方にとって重要な課題とし、社員への認知活動、社内制度の見直しなど、あらゆる取り組みが日々研究されています。このように、ワーク・ライフ・バランスは、単に時間の配分に留まらず、働く人々の生活の質を向上させるための包括的なアプローチとして社会に浸透しはじめてきているのです。
ワーク・ライフ・マネジメント vs ワーク・ライフ・バランス
ワーク・ライフ・マネジメントとワーク・ライフ・バランスは、一見似ているようで異なる概念です。まず、ワーク・ライフ・バランスとは、仕事と私生活の調和を目指す考え方です。一方、ワーク・ライフ・マネジメントは、個人が自らの時間を効果的に管理し、仕事と私生活の双方を最適に運営するためのスキルや戦略を指します。つまり、ワーク・ライフ・バランスが個人の生活の質を高めるための環境整備であるのに対し、ワーク・ライフ・マネジメントはその環境を活用して自己管理を行うプロセスといえるでしょう。
この二つのアプローチは、相互に補完し合う関係にあり、どちらか一方だけではなく、両方を取り入れられれば、より効果的な結果を生むことができます。たとえば、企業がワーク・ライフ・バランスを促進するためにフレックスタイム制度を導入したとしても、従業員が自己管理能力を欠いていると、その制度の恩恵を十分に受けられません。そのため、企業は制度の提供だけでなく、従業員に対する時間管理や優先順位設定のスキルを向上させるためのトレーニングも必要となります。
また、ワーク・ライフ・マネジメントは、単に勤務時間を効率化するだけでなく、ストレス管理や休息の重要性にも焦点を当てています。自己管理能力を高めることで、従業員はストレスを軽減し、仕事における生産性を高められるのです。したがって、組織はこれらの概念を理解し、実践することで、持続可能な労働環境の構築が求められます。
ワーク・ライフ・インテグレーション vs ワーク・ライフ・バランス
ワーク・ライフ・インテグレーションとワーク・ライフ・バランスは、どちらも仕事と私生活の調和を目指す概念ですが、そのアプローチには大きな違いがあります。ワーク・ライフ・バランスは仕事と生活のそれぞれに適切な時間とエネルギーを配分することで、両者のバランスを保つことを重視します。このモデルは、オフィスの勤務時間が終わったら、仕事を完全に切り離して家庭や趣味に集中するという考え方が基本です。
一方、ワーク・ライフ・インテグレーションは、仕事と私生活を一体化して考え、状況に応じて柔軟に時間を使うことを推奨します。例えば、日中に個人的な用事を済ませ、夜に仕事をするなど、場所や時間にとらわれない働き方も、この概念が生み出したものです。テクノロジーの進化により、リモートワークが可能になり、仕事の時間と場所を柔軟に選択可能になったように、このモデルは、個人のライフスタイルに応じて仕事を組み込むことで、より高い効率性と満足度を追求します。
しかしながら、どちらのアプローチも一長一短があります。例えば、ワーク・ライフ・バランスは明確な境界線を引くことで精神的なリフレッシュが可能ですが、固定的な時間管理が求められるため、急な仕事の変更には対応しづらい場合があります。対して、ワーク・ライフ・インテグレーションは柔軟性を提供する一方で、仕事と私生活の境界が曖昧になり、常に仕事に縛られている感覚に陥るリスクも伴います。ですから、一つの考え方だけに固執するのでなく、個々のライフスタイルや価値観に応じて、どちらのアプローチが自分に適しているかを見極めるのが重要だ、ということを忘れないでください。
ワーク・ライフ・バランスの重要性
この章では、ワーク・ライフ・バランスをなぜ社会が重要視し始めたのかについて、現代社会における必要性と、企業がそれを検討するメリットの2つの観点から見ていきましょう。
現代社会におけるワーク・ライフ・バランスの意義
上記の『ワーク・ライフ・バランス』の定義で見たように、現代社会において、ワーク・ライフ・バランスは単なる個人の生活の質を向上させるための手段としてだけではなく、社会全体の健全な発展に寄与する重要な要素として位置づけられています。特に最近はリモートワークを推奨する企業が増えたことにより、仕事の柔軟性は増しましたが、時間や場所に縛られない働き方が可能になったため、仕事とプライベートの境界が曖昧になりがちです。また、デジタル化が進む中で、情報過多やオンラインでの過剰な接続性は、個人の健康においても新たな問題を生み出しています。このため、ワーク・ライフ・バランスを保つことが、ストレスの低減や精神的健康の維持に直結しているのです。また、従業員が満足し、充実した生活を送ることができれば、結果として生産性が向上し、企業や社会全体の持続可能な成長につながります。
さらに、ジェンダー平等や多様性の観点からも、ワーク・ライフ・バランスの確保は不可欠です。例えば、育児や介護の負担が特定の性別や個人に偏ることなく、全ての人が公平に責任を分担できる環境の整備が求められています。これにより、労働力の多様性が促進され、異なる視点やアイデアが組織に活かされ、革新や創造性が生まれるのです。
上記のことから、現代におけるワーク・ライフ・バランスの意義は、個人の幸福を超えて、より広範な社会的な価値を生み出す力を持っていると言えるでしょう。
企業がワーク・ライフ・バランスを充実化させるメリット
企業がワーク・ライフ・バランスを充実させることには、多くのメリットがあります。
まず、従業員の満足度やモチベーションが向上することで、離職率が低下し、採用や研修にかかるコストを削減できます。満足した従業員は生産性が高く、創造性を発揮しやすくなるため、組織全体の業績向上にもつながります。また、競争が激化する現代のビジネス環境において、優秀な人材を惹きつけ、維持するためには、柔軟な働き方の提供が強力な魅力の一つとなります。さらに、ワーク・ライフ・バランスを重視する企業は、社会的責任を果たしていると認識され、ブランドイメージの向上につながります。これにより、顧客やパートナー企業からの信頼を獲得し、ビジネスチャンスの拡大に寄与するでしょう。もちろん、従業員が心身ともに健康であることは、ストレスや過労による健康問題を未然に防ぐため、持続可能な経営を実現する一助となります。
また、国や自治体による支援制度や補助金の対象となることもあるため、財政的なメリットもあるのが、企業にとっては注目すべき理由です。このように、企業がワーク・ライフ・バランスを充実化させようとすればするほど大きなメリットを享受できるため、積極的に取り組むべき課題といえるでしょう。それでは、具体的にどのようなアクションを取るべきなのでしょうか?次の章では、推進法について見ていきます。
7割が“うまく活かせていない”と回答した理由は?」
他社の苦悩とヒントが見える、共感性の高い調査レポートをDL ▶
ワーク・ライフ・バランスの具体的な5つの推進法

この章では、企業がワーク・ライフ・バランスを推進するにあたり、従来のものから最新の手法まで、以下の5つに焦点を当てて解説していきます。
-
労働時間を管理する
労働時間の管理は、ワーク・ライフ・バランスを推進するための基盤的な施策です。まず、企業は従業員の労働時間を適切に把握し、長時間労働を未然に防ぐためのシステムを導入することが求められます。具体的には、タイムカードや勤怠管理ソフトを活用して、実際の労働時間を正確に記録し、定期的に分析することで、過労のリスク削減が可能です。また、フレックスタイム制度やシフト制の導入で、従業員が個々のライフスタイルに合わせた働き方を選択できるようにし、仕事と生活の調和を促進します。
さらに、定期的な労働時間の見直しを行い、業務の効率化を図るのも重要です。これには、無駄な会議の削減や業務プロセスの最適化が含まれます。業務効率化の推進により、従業員は限られた時間内で成果を上げられるようになり、結果的にプライベートの時間を確保しやすくなるでしょう。
従業員に対しては、自己管理能力を高めるための研修やワークショップを提供することも効果的です。自らの時間を効率的に管理するスキルを身につけることで、個々の従業員が主体的に働き方を改善する意識を持つようになります。
また、企業文化として、労働時間の柔軟性を尊重する姿勢を醸成することも忘れてはなりません。上司や同僚が率先して定時退社を実行し、休暇を積極的に取得する姿勢を見せれば、職場全体に健康的な働き方を推奨する雰囲気が生まれます。労働時間の管理を徹底することは、従業員の心身の健康を維持し、結果的に企業の生産性向上にもつながるのです。
-
労働時間を改善する
労働環境の改善は、ワーク・ライフ・バランスの向上において重要な要素です。まず、物理的な環境の見直しが必要です。快適な作業スペースを提供することで、従業員の集中力や生産性が向上します。例えば、適切な照明、エルゴノミクス(人間工学)に基づいたオフィス家具の導入、空調や騒音対策などが挙げられます。
次に、心理的な環境の改善も欠かせません。オープンで協力的な職場文化を醸成すれば、従業員同士のコミュニケーションが円滑になり、ストレスの軽減が期待できます。また定期的なミーティングやフィードバックの場を設ければ、従業員の声を反映しやすくし、彼らの満足度向上につながるでしょう。
さらに、柔軟な働き方を推進するのも労働環境の改善に寄与します。フレックスタイム制度やリモートワークの導入により、従業員は自分のライフスタイルに合わせた働き方が可能となり、仕事へのモチベーションも高まります。また、ストレスマネジメントのためのメンタルヘルスケアプログラムを提供することによる従業員の健康維持サポートも重要です。
-
柔軟な働き方を実現!在宅勤務制度を導入する
在宅勤務制度は、柔軟な働き方を実現するための重要な手段です。まず、在宅勤務制度を導入する前に、企業は明確な方針とガイドラインを策定し、従業員にその詳細を周知することが必要です。これにより、働く場所に関する選択肢を広げ、従業員が自分のライフスタイルに合わせた働き方を選択できるようになります。
次に、適切なテクノロジーの整備が不可欠です。リモートワークを可能にするためには、オンライン会議ツールやプロジェクト管理ソフトウェアの導入が求められます。また、セキュリティの観点から、データ保護のためのVPNや二要素認証の整備も重要です。
一方で、在宅勤務を成功させるためには、コミュニケーションの維持が重要です。定期的なオンラインミーティングやチャットツールを活用して、チーム内の情報共有と連携を強化するなどの工夫をすることで、たとえ物理的に遠くても、より意思疎通がしやすくなるのを実感するでしょう。さらに、離れているからこそ、日ごろから従業員のメンタルヘルスにも配慮し、必要に応じてサポートを提供することが望ましいです。
-
育児休暇や育児支援制度を導入する
育児休暇や育児支援制度の導入は、ワーク・ライフ・バランスを推進する上で重要な要素です。これらの制度は、特に子育てをする従業員にとって、仕事と家庭の両立を支援する役割を果たします。育児休暇は、出産後の休暇期間を確保するだけでなく、その後の育児期間にも柔軟に対応できるように設計されていることが望ましいです。また、育児支援制度には、育児手当の支給、育児休業中のキャリア形成支援、育児関連のセミナーやワークショップの開催などが含まれます。このような制度を導入すれば、企業は従業員の離職率を低下させ、育児中の社員が安心して職場に復帰できる環境を整えることができます。
さらに、育児支援制度は、企業のイメージアップにも寄与します。現代の求職者は、働きやすさや家庭との両立を重視する傾向が強まっており、育児支援制度が充実している企業は、優秀な人材を引き寄せる可能性が自然と高まります。また、育児を理由にキャリアを中断せずに済むため、社員は長期的な視点で企業に貢献しやすくなり、結果として企業の競争力向上につながる、といった背景が挙げられます。
ワーク・ライフ・バランスの各企業の具体的な取り組みは、内閣府の以下のページでも紹介されていますので、他社事例も参考にして自社の取り組みを考えてみましょう。
参考:内閣府「『仕事と生活の調和』推進サイト」 -
勤怠管理データを活用した独自施策を実施する
ワーク・ライフ・バランスを推進するためには、勤怠管理データの活用が不可欠です。このデータは、従業員の出退勤時間や残業時間を正確に把握するための基本情報として機能します。具体的には、勤怠データを分析し、労働時間の偏りや不規則な勤務パターンを明らかにでき、適切な対策を講じることが可能になります。例えば、業務のピーク時や特定の曜日に過度な労働が集中している場合、シフトの調整や業務の再分配を検討することができます。
さらに、勤怠管理データは、従業員の健康管理やモチベーションの向上にも役立ちます。過労による健康リスクを未然に防ぐために、従業員の勤務時間を定期的にモニタリングし、必要に応じて休暇を促せます。また、データに基づくフィードバックを行えば、従業員一人ひとりの働き方を尊重し、より良い労働環境を提供することができるのです。
このように、勤怠管理データの利用は、単なる時間管理を超えて、企業文化の改善や人材の育成にも寄与する、大きな可能性を秘めた手法です。ですが、こうしたデータを蓄積し、効果的に分析や活用を行うにはBI(ビジネス・インテリジェンス)ツールが必要不可欠となります。BIツールについては、次の章で詳しくご紹介しましょう。
BIツールとは何か
企業がデータを活用し、社内体制やビジネスの成長につなげたいなら、BIツールの活用が一般的となりつつあります。この章では、BIツールの主な役割や、最新のBI事情について簡単に解説していきます。
BIツールの基本的な機能
BIとは、Business Intelligenceの頭文字を取ったものです。BIツールの基本的な機能は、企業がデータを効率的に収集し、分析し、視覚化することを可能にする点にあります。まず、データ収集機能では、様々なソースから情報を自動的に取り込むことができます。これには、社内のデータベースや外部のクラウドサービス、さらにはソーシャルメディアなどが含まれ、データの一元管理が可能です。
次に、データ分析機能では、収集した膨大なデータを整理し、意味のあるインサイトを導き出すことが可能です。これには、統計分析や予測分析、データマイニングの手法が用いられ、ビジネス上の意思決定をサポートします。また、ダッシュボードやレポート機能を通じて、分析結果をわかりやすく視覚化することもできます。これにより、複雑なデータもシンプルに表現され、迅速な判断が可能になります。
最近ではAI(人工知能)予測機能による、より精緻な将来に向けた戦略策定が促されるようになるなど、従来のBIからは変化し、誰でも簡単に高度な分析結果が得られる仕様へと様変わりを遂げているのが特徴です。
最近のBIツール事情とトレンドとは
近年、BIツールは飛躍的に進化を遂げ、よりユーザーフレンドリーかつ高度な分析機能を持つようになっています。AI(人工知能)や機械学習の技術が統合され、自動的にデータの傾向を分析したり、異常値を検出したりする機能が増えています。こうした豊富で使いやすい機能が多く登場してきたおかげで、データサイエンティストだけでなく、一般のビジネスユーザーも簡単に高度な分析を行えるようになったのは、大きな進歩と言えるでしょう。また、現在ではクラウド化が進み、オンプレミスのシステムと比べて導入コストが抑えられるため、スケーラビリティやアクセスの柔軟性が向上したのも導入に拍車をかけています。
利便性の面で言えば、モバイル対応が進んでいるツールも多くリリースされており、スマートフォンやタブレットからでも容易にデータにアクセスし、意思決定を行うことができるのも魅力です。また、ダッシュボードのカスタマイズ性が向上し、ユーザーのニーズに応じたインターフェースも、IT部門以外の社員でも容易に行えるツールが出ているため、そうしたツールを選べばテクノロジーの恩恵を最大限に受けながら、ビジネスの成長を加速させられるのです。
これらの機能を搭載しているBIツールの代表格に、Domo(ドーモ)というツールがあります。
このように、BIツールはますます多様化し、企業のさまざまなニーズに応えるための重要なツールとなっています。企業が競争優位を維持するためには、BIツールを活用し、データに基づく意思決定を行うことが不可欠です。
以下の資料では、今最も注目を集めている8つのBIツールを、ユーザーニーズや機能面から比較しました。最近のBIツールのトレンドも詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。
ビジネスにおけるBIツールの役割
BIツールは、ビジネスの意思決定をデータに基づいて行うための強力なサポートを提供します。
例えば、売上データや顧客の行動パターンを分析し、ビジネスのパフォーマンスを可視化します。これにより、企業はどの製品やサービスが最も利益を生んでいるのか、どの地域での販売が伸びているのかを直感的に理解できるようになるのです。また、BIツールは予測分析を通じて将来のトレンドを予測し、リスクを最小限に抑えるための戦略的計画にも活用できます。
また、BIツールは部門間のコミュニケーションを強化する役割も果たします。なぜなら、データを可視化し、同じダッシュボードを見ながら会話ができる環境づくりをすることで、異なる部門の担当者が共通の理解を持ちやすくなり、協力体制の強化につながるからです。
さらに、BIツールは効率的なレポート作成を支援し、定期的な業績報告を迅速に行えるようにします。結果として、企業全体の運営効率が向上し、競争力が増すため、長期的に見て、もはやビジネスにおいて必要不可欠なツールとなっているのです。
働きやすさを仕組みで支える、7つの構造改革要素
組織文化を変える“理論と実践”をまとめたガイドをDL ▶
ワーク・ライフ・バランス充実化にBIツールが必要な理由

ワーク・ライフ・バランスの充実化において、BIツール(Business Intelligenceツール)は不可欠な要素となってきています。これまでは、データの収集や集計くらいしかやっていなかった企業にとって、収集した膨大なデータを分析し、可視化することで、従業員の働き方や企業の生産性を向上させるための具体的な施策アイデアが、もっと豊富に思いつくようになるのを実感できるでしょう。この章では、BIツールをどのように活用すれば、ワーク・ライフ・バランスの充実化に効果的なのかについて、解説します。
勤怠データを活用すると業務の無駄が省ける
BIツールを活用して勤怠データを分析することは、業務の効率化において非常に有効です。多くの企業が、従業員の労働時間や休憩時間を正確に把握することで、業務の流れを見直し、無駄を削減しています。例えば、特定の時間帯に業務が集中しすぎている場合、勤怠データの分析結果を基にシフトを最適化できます。これにより、従業員の過度な負担を軽減し、全体の生産性を向上させることが可能です。
また、勤怠データを詳細に分析すれば、従業員がどのような業務にどれだけの時間を費やしているかを把握できます。これにより、不必要な業務やプロセスを特定し、業務の簡素化や自動化を図れます。
さらに、定量的なデータに基づいた改善策を講じることで、業務の透明性を高め、従業員のモチベーション向上にも寄与します。
勤怠データの分析は、単に労働時間を管理するだけでなく、休暇の取得状況や残業の傾向も把握可能です。これにより、従業員の健康管理やメンタルヘルスの維持にも役立ちます。例えば、特定の従業員が過度に残業している場合、その原因を突き止め、適切な対策を講じることで、個々のワーク・ライフ・バランスを改善できます。
従業員の働きやすい環境の構築づくりが行える
従業員の働きやすい環境を構築するためには、個々のニーズや業務の特性を把握し、それに応じたアプローチを取ることが重要です。例えば、特定の業務に時間がかかりすぎている従業員には、スキルアップのための研修を提供したり、作業の自動化を検討したりできます。このようなケースから分かるように、残業時間が多い従業員を役職別、部署別、または個人リストを作成し、毎月または月次推移などで様子を観察できるようにすると良いでしょう。
また、従業員のストレスレベルや離職率に関するデータを分析することで、メンタルヘルスをサポートするための施策を導入することも可能です。さらに、BIツールによって集約されたデータは、経営層と従業員の間でのコミュニケーションを促進し、よりオープンで協力的な職場環境を作り出す手助けにもなります。
ワーク・ライフ・バランス充実化に向けたBIツール活用事例
この章では、ワーク・ライフ・バランス充実化を実現するため、企業がどのようにBIツールを導入し、活用しているかをご紹介します。
事例①残業過多による社員の疲弊が深刻化した建設会社
建設業界では残業が多くなりがちであり、社員のワーク・ライフ・バランスの充実化が以前から訴えられています。特に、36協定の遵守や勤怠管理の適正化は迅速に解決しなければならない問題として取り上げられており、ある建設企業はBIツールの導入に向けて動き出しました。
| 【実施したこと】 | 社内基幹システムや各種SaaSからの情報を、もともと勤怠管理用に人事が利用していたkintone(キントーン)環境へ集約。社員データを一元化し、分析環境までを整備したデジタルトランスフォーメーションを推進しました。 |
| 導入効果 |
BIツールの代表製品であるDomo(ドーモ)を活用することで、業績の計画と日々の実績をリアルタイムで可視化し、迅速な経営判断が可能になりました。 また、勤怠データの適正管理により、36協定の遵守が徹底され、社員の休暇取得状況も適正に管理されるようになったのです。これにより、社員の満足度が向上し、今後も企業の持続可能な成長が期待されています。 |
事例②在庫管理が想像以上の工数負荷だと浮彫りとなった卸・小売会社
卸・小売業界では、在庫管理の方法次第で従業員の勤務負荷状況をさらに圧迫することになります。ある卸・小売業を経営する企業では、在庫の棚卸業務に膨大な時間がかかっているほか、滞留在庫が多くキャッシュフローにも悪影響を及ぼしていたため、BIツール導入による改善に踏み出しました。
| 【実施したこと】 | 時間のかかっていた棚卸業務は、在庫データをBIツールのDomo上で倉庫のレイアウトに合わせてマッピングし、状況を色で表現し、在庫状況を把握するようにしました。さらに勤怠データもBIツールのダッシュボードで視覚的に管理するようにし、これまでの集計作業も削減しました。 |
| 導入効果 |
なぜ時間がかかるか原因が不明だった在庫管理業務が、視覚的に管理されるように改善したことにより、滞留在庫が大幅に削減されたほか、キャッシュフローが改善されたのは大きな功績でした。 また、従業員の勤怠管理レポート作成工数も削減され、全社で集中すべき作業に取り組めるようになりました。 |
人事・経企が実現した“見える化”の成果とは?」
従業員データを活かした具体的な改善事例をまとめた1冊 ▶
BIツールの導入5ステップ

BIツールの導入は、企業の業務効率化やデータ駆動型意思決定をサポートする重要なプロセスです。主に以下5つのステップで行います。
- ニーズの洗い出しとBIツール選定基準の決定
- BIツールの選定
- ツールの導入計画策定
- 社内トレーニング
- 定期的な評価と改善
ステップ1:ニーズの洗い出しとBIツール選定基準の決定
まず、導入の第一歩として、企業内のニーズを明確にすることが不可欠です。どの業務を改善したいのか、どのデータを分析する必要があるのかを洗い出すことで、BIツールの選定基準が定まります。
ステップ2:BIツールの選定
次に、適切なBIツールを選ぶフェーズに移ります。市場には多様なBIツールが存在するため、それぞれの機能や特長を比較し、自社の要件に最も合致するものを選択します。
ステップ3:ツールの導入計画策定
選定後は、ツールの導入計画を策定し、プロジェクトのスケジュールや担当者を決定します。導入に際しては、IT部門と業務部門と連携し、データのインテグレーションやシステム連携をスムーズに行うための技術的サポートの確保や、必要なインフラを整備しましょう。ツールの設定やカスタマイズを進める段階では、業務プロセスに即したダッシュボードやレポートを作成し、社員が使いやすいインターフェースを構築します。
ステップ4:社内トレーニング
導入後は、社員へのトレーニングが重要です。BIツールを効果的に活用するためには、社員がその操作方法やデータの解釈に精通している必要があります。トレーニングプログラムを実施し、継続的なサポート体制を整備することで、ツールの利活用が定着するので、初期段階での社内認知計画もしっかりと行いましょう。
ステップ5:定期的な評価と改善
最後に、導入したBIツールの効果を定期的に評価し、必要に応じてツールやプロセスの改善を図ります。これにより、ワーク・ライフ・バランスの向上や業務効率化を実現し、企業全体の持続的な成長が促されるので、導入後も社内の利用状況、問い合わせ窓口の設置、勉強会など、従業員が積極的に業務の中で利用し、活用方法について研究していくと良いでしょう。
もっと迅速な導入を目指すなら、テンプレートを活用しよう

「BIツールを導入しても、どんなグラフやダッシュボードを用意すれば良いのか分からない」。そんなユーザー様のお悩みを解決するため、弊社はDomoを利用した、独自のクイックスタートテンプレートをご用意しております。経営者や人事部、部門長は労働時間の超過や有給休暇の取得状況を一目で把握できるようなダッシュボードには、基本の型があります。
【基本の勤怠管理項目例】
| 管理項目 | 利用用途 |
|---|---|
|
労働時間の現状把握に利用。賃金算出の際には、始業・終業時間を1分単位で管理。遅刻、早退の多い従業員への業務指導や配置転換検討もこのデータから行う。 |
|
法定労働時間を超えた労働時間に対する賃金支払いを行う。また時間外労働や深夜労働、休日労働には割増賃金を適用する。 |
|
月単位での従業員勤務状況把握に利用。休暇取得状況、振替休日や代休取得状況の確認や給与計算に用いる。 |
|
適切な休暇が取得されているか、就業環境の適正化を確認する。 |
本テンプレートは、その基本の型に乗っ取って誰でも簡単にダッシュボードを作成できるよう、事前に作成されたデータフローやカードのテンプレートを提供し、お客様のデータ活用を迅速かつ効果的に実現します。
Domoについては、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

|
【関連記事】 |
もちろん、事前に弊社の専門担当者がヒアリングを行い、導入を支援するため、自社独自のダッシュボードが必要な方にも安心してご利用いただけます。詳しくはぜひお問い合わせください。
まとめ
この記事では、BIツールの導入ステップを中心に、ワーク・ライフ・バランスの重要性やその推進方法についても詳しく解説しました。
ワーク・ライフ・バランスは現代社会での働き方改革において重要な概念であり、企業がそれを充実させることによって得られるメリットは計り知れません。労働環境の改善や柔軟な働き方の実現は、従業員の満足度や生産性向上に寄与するため、企業戦略の一環として取り組むべきです。
また、BIツールの導入は、勤怠管理データの活用を通じて業務の効率化を図る上で非常に効果的です。BIツールは、単なるデータの集計・分析を超えて、従業員一人ひとりが働きやすい環境を構築するための強力なツールとなります。成功事例として紹介した企業のように、適切なBIツールを活用することで、業務プロセスの改善や企業全体のパフォーマンス向上が期待できます。
企業が競争力を維持し、さらなる成長を遂げるためには、DomoをはじめとするBIツールを活用したデータドリブンなアプローチが不可欠です。さらに、基本のグラフなどが既に設計されている、ダッシュボードテンプレートを利用すれば、よりスムーズに社内導入が可能となります。
この記事を通じて、BIツールの導入によって得られる可能性や、ワーク・ライフ・バランスの向上に向けた具体的な手法について理解を深めていただけたでしょうか。これらの知識を活用し、企業の持続的な発展に役立てていただければ幸いです。
NDIソリューションズでは、BIプラットフォーム Domoを利用した企業事例集の公開、セミナーの開催を行っております。
Domoまとめて導入事例集
Domoセミナー / イベント情報
また、実際にDomoを動かしていただけるBI無料トライアルもご用意いたしました。ご興味がある方はぜひ上部メニューよりお申し込みください。
当サイトでは、BIツールに興味のある方へ、参考になるダウンロード資料をご用意しております。「BIツール初心者向けまるわかりガイド」と「統合型BIプラットフォーム Domo基本ガイドブック」は、データ活用やBIツール導入のポイントが把握できる資料になっています。BIツールご検討の参考に、ぜひダウンロード資料をご覧ください。
公開日:2025年3月11日
ワークライフバランス
- ワーク・ライフ・バランス充実化の最前線|BIデータ活用とは