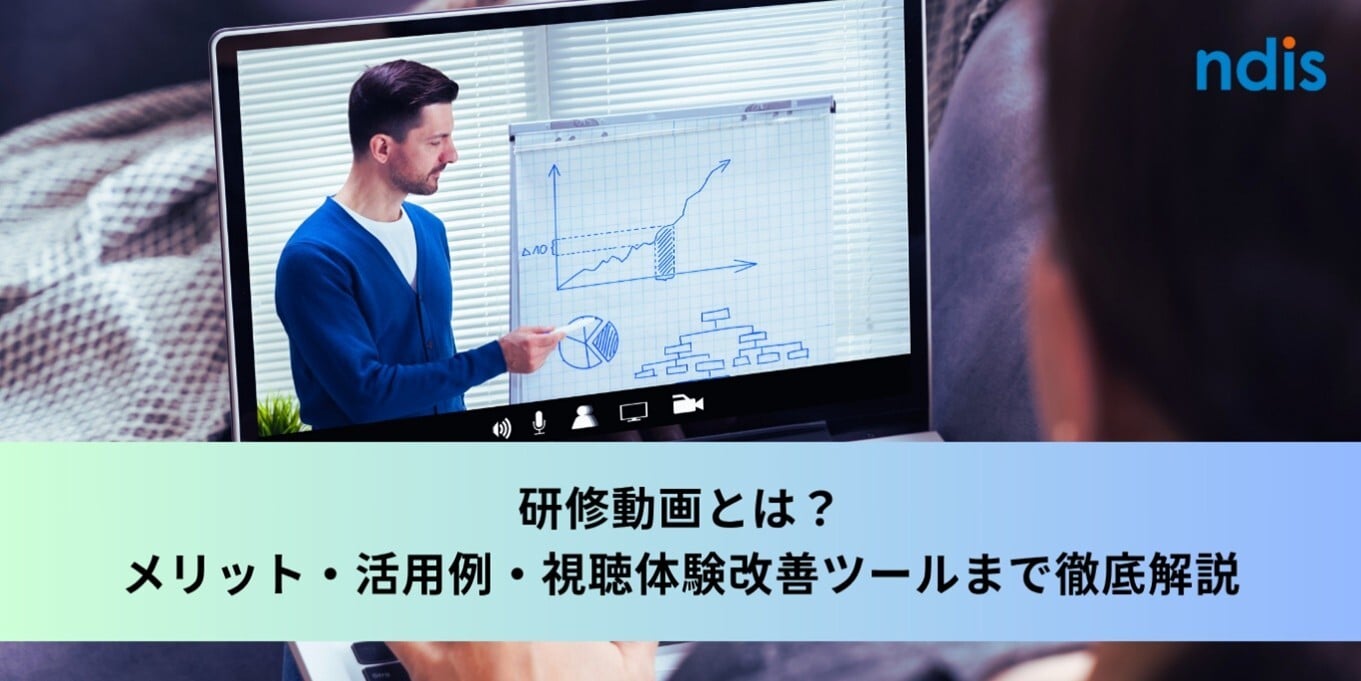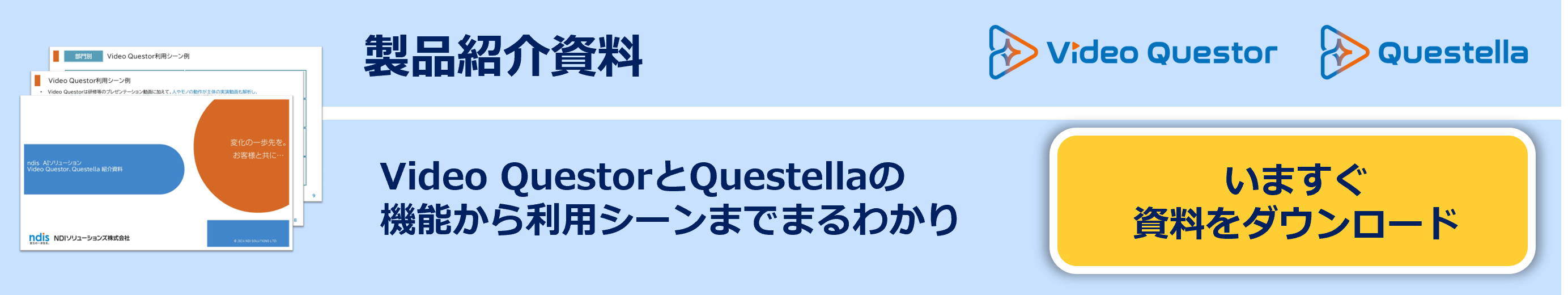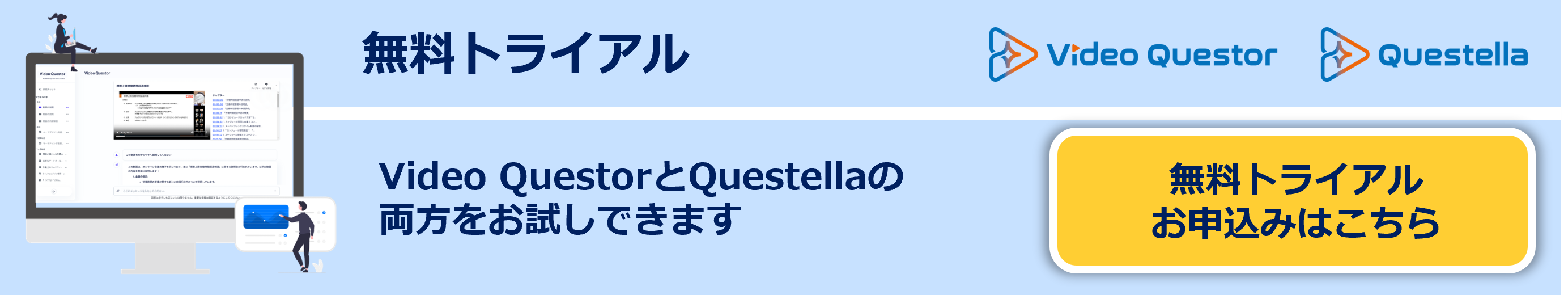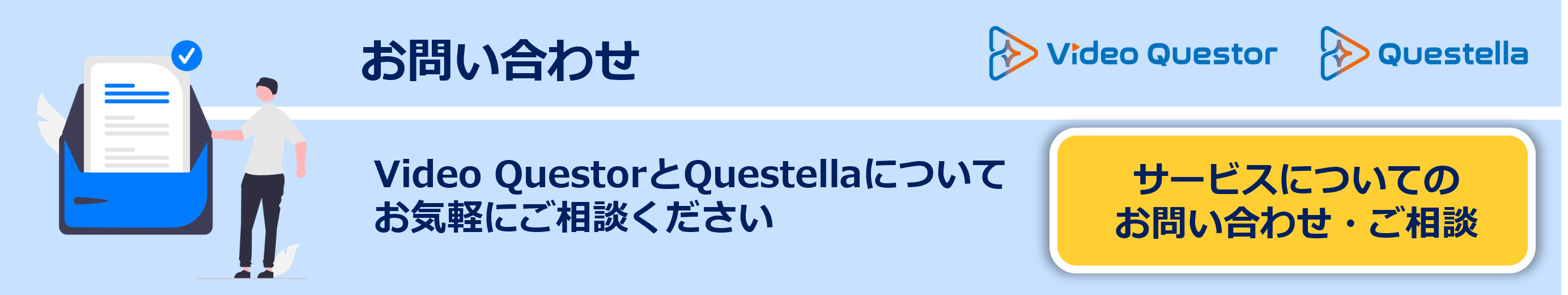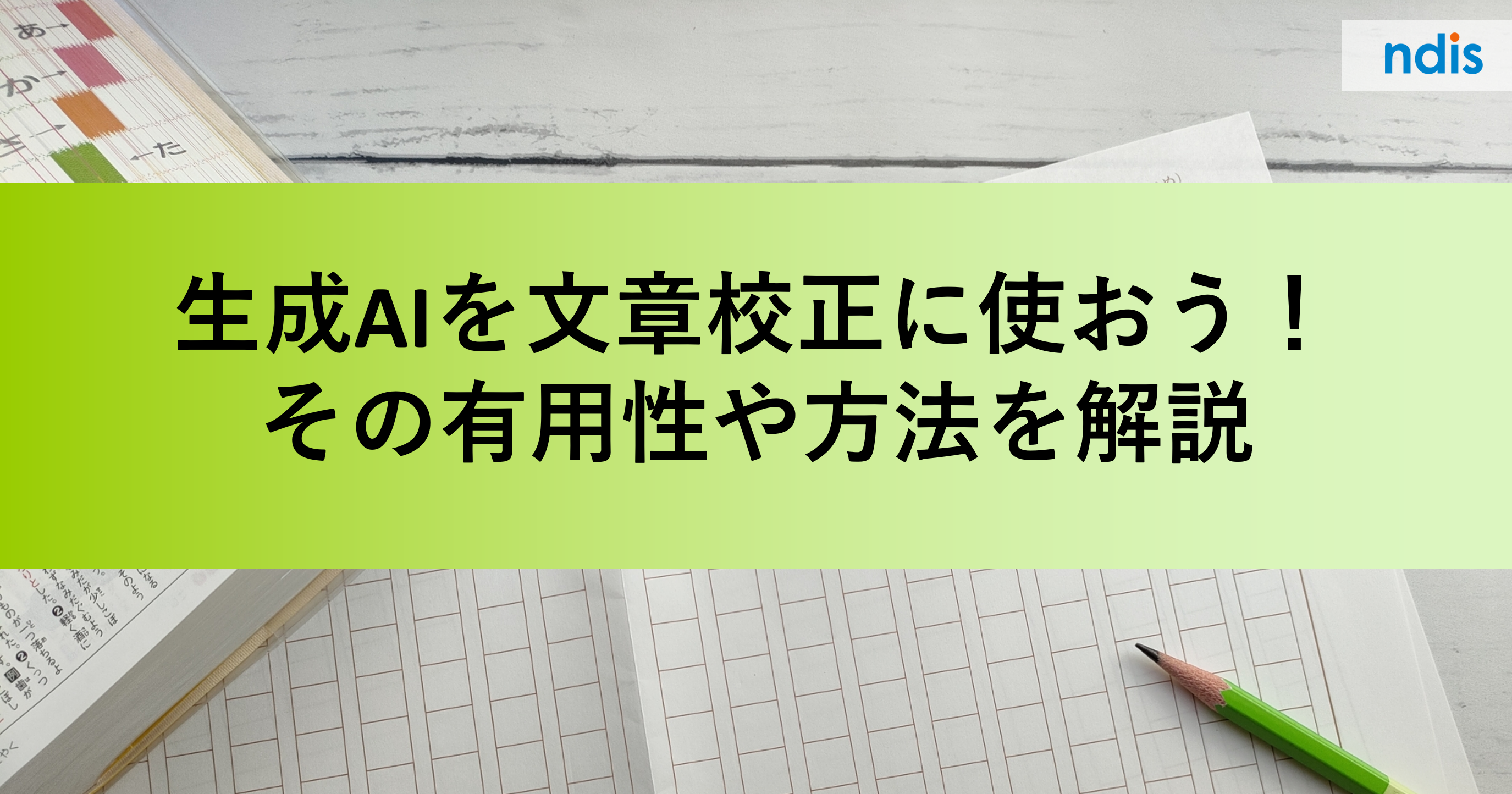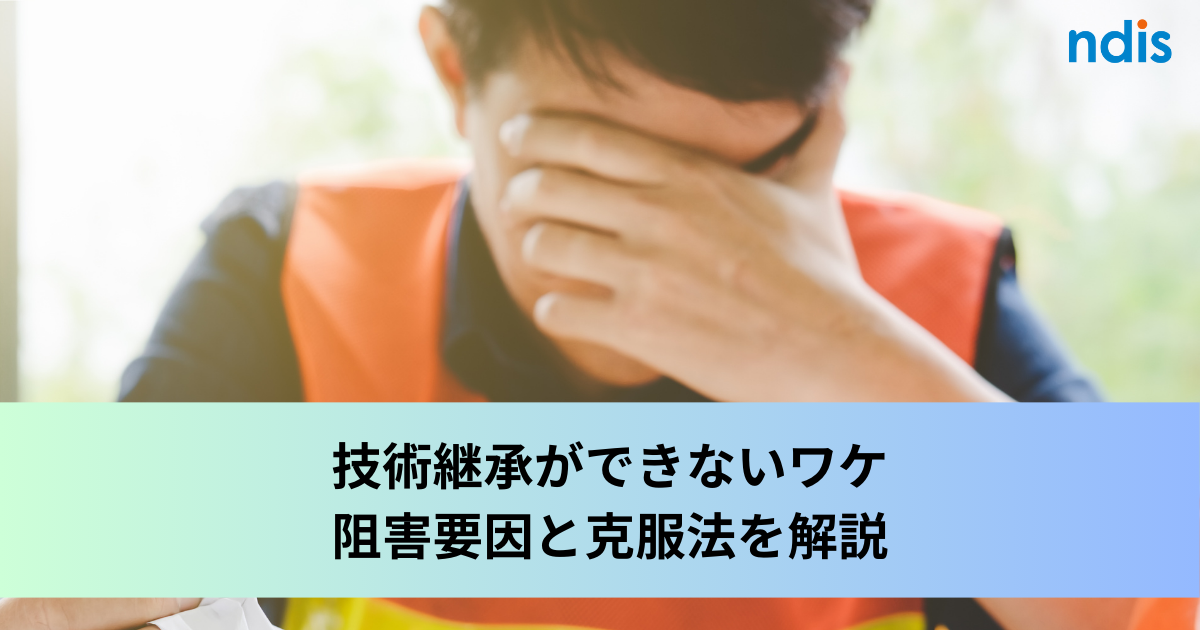無料生成AIに関する人気資料をまとめてダウンロードできます。
近年、研修動画を活用した社内研修/オンライン研修の導入が多くの企業で進んでいます。従来の集合研修に比べてコストを抑えながら、社員それぞれに対応できる個別化も可能になるからです。
本記事では、研修動画の定義や種類、メリット・注意点、実際の活用シーン、効果測定方法、さらに視聴体験を強化するツールを交えて、企業が押さえるべき研修動画導入のポイントを解説します。
研修動画の基本とは
研修動画の定義と目的
研修動画とは、視覚と聴覚の両方を活用して、学習者に特定の知識やスキルを伝える映像コンテンツを指します。企業や教育機関では、従業員や学生の能力向上を目的に利用されることが一般的です。
主な目的は以下のとおりです:
- 理解促進:テキストや口頭での説明だけでは伝わりにくいプロセスや手順、複雑な概念を映像やアニメーションで示す
- 繰り返し学習:動画は何度も見返せるため、学習者が自分のペースで理解を深められる
- 教育の標準化:講師による教え方の差をなくし、企業内で統一された教育を提供
- 柔軟な学習環境:時間・場所を問わず視聴可能で、オンライン研修にも対応
このように、研修動画は単なる補助教材ではなく、現代の企業教育において中心的な役割を担い得るツールです。
研修動画の種類と特長
以下は、用途や目的に応じた代表的な研修動画の種類です。
表では、「学習内容」と「提供形式」の両面から代表的な研修動画の種類を紹介しています。
| 種類 | 特長・目的 | 利用シーン |
| 基礎研修動画 |
業務の基本知識・基礎スキルを学ぶ |
新人研修、業務ルールの共通理解 |
| 専門研修動画 |
特定のスキルや知識を深める |
技術職研修、資格対策、専門業務 |
| 実践型研修動画 |
ケーススタディ・シミュレーション形式 |
問題解決力・判断力の強化 |
| ソフトスキル研修動画 |
リーダーシップ・コミュニケーション等 |
管理職研修、チーム育成 |
| オンデマンド研修動画 |
オンライン配信型、受講者主導型 |
自己啓発、補填学習 |
| インタラクティブ研修動画 |
クイズ・分岐・応答など参加型 |
視聴者の理解確認、能動的学習 |
研修動画の選択は、目的や対象者、予算と時間などを考慮して適切に行う必要があります。
研修動画のメリット
学習効果の向上
研修動画は、「社員のスキルアップや教育の効率化」に効果的です。映像と音声を組み合わせた表現によって、テキストだけでは伝わりにくい内容もわかりやすく伝えられます。さらに、受講者は自分のペースで再生・一時停止・巻き戻しを行えるため、学習の自由度が高まります。
また、視覚的な演出やナレーション、インタラクティブ要素を活用すれば、受講者のエンゲージメントを刺激でき、記憶への定着も促されます。さらに、すべての社員に同じ動画を提供できる点から、講師の違いによる内容のばらつきや拠点間の教育格差を防ぎ、企業内教育を標準化できます。
こうしたメリットにより、動画研修は多くの企業で採用されており、DX 推進にも寄与する可能性がある教材方式となっています。
コスト削減と効率化
動画研修を導入する企業は、従来型集合研修に伴う費用負担を抑えられます。会場費、講師派遣、資料印刷、参加者の交通費などが省けるため、運用コストが大幅に削減できます。
動画は一度作れば何度でも再利用可能であり、社員は空き時間や出張中など、自由なタイミングで視聴できます。特に社内研修やオンライン研修では、この「いつでも視聴可能」な特性が大きな強みになります。
また、動画を LMS(学習管理システム)と連携すれば、視聴履歴の把握や管理も容易になり、研修運用の効率化が進みます。進捗可視化や受講率管理を自動化すれば、研修担当者の負荷を軽減できます。
今さら聞けない基本用語とリスクを総まとめ
生成AI 基本の『き』
研修動画のデメリットと注意点
制作コストと時間
研修動画の制作には、一定のコストと時間が必要です。外部に委託すれば高品質な研修用動画ができますが、多額の費用がかかります。また、内製するにしても、撮影機材や編集ソフト、ナレーション収録、専門スタッフの手配などが発生し、予算が膨らむ可能性があります。ただし、すべてを外注せずに、社内リソースを活用した簡易な研修動画であれば、コストを抑えつつ制作することも可能です。
また、研修動画の制作工程には、企画、台本作成、撮影、編集、レビューといった段階が含まれ、それぞれに時間を要します。制作チームの経験やプロジェクトの規模によって、完成までの期間には差が出ますが、最近ではAIや自動化ツールの活用によって、字幕生成や編集作業の効率が向上しており、制作時間を短縮する手法も広がっています。
さらに、研修動画を公開する際の運用面でも、配信スケジュールの調整、プラットフォームの選定、社内周知など、事前の準備が不可欠です。これらの準備が不十分なまま運用を開始すると、視聴率の低下や理解度のばらつきを招く恐れがあるため、計画的な導入が求められます。
受講者のモチベーション維持
研修動画は、便利で柔軟な学習手段である一方で、受講者のモチベーションが低下しやすいという課題もあります。特に、長時間にわたる一方通行の情報提供や、単調なスライドのみで構成された研修動画は、集中力の維持が難しく、結果的に学習効果の低下を引き起こします。
このような課題に対しては、研修動画の構成や演出に工夫を加えることが重要です。たとえば、インタラクティブな要素を取り入れれば、受講者能動的な参加を促進し、理解の定着をサポートできます。具体的には、動画内にクイズや選択式の問いかけ、リアクションボタンなどを配置する手法が有効です。
また、実際の業務に即したケーススタディや、現場のシナリオを活用すると、自身の業務との関連性を感じながら学べるため、受講者の関心を維持しやすくなります。研修動画の視聴後には、質疑応答やディスカッションの場を設けることで、内容の定着や深い理解を促すのも有効です。
さらに、コメント機能やチャット機能を活用したオンライン交流によって、受講者同士が意見を交わす機会を生み出すことも効果的です。受講者の「参加したくなる」気持ちを高めるためには、構成や表現の工夫が不可欠です。
セキュリティリスク
研修動画の運用では、セキュリティ対策も重要な検討項目です。特に、機密情報や社員の個人情報が含まれる可能性があるため、情報漏洩リスクを常に意識する必要があります。
研修用の動画データの保存や転送時には、暗号化技術を導入し、不正アクセスの防止徹底が求められます。また、視聴対象を限定するには、アカウントごとの認証設定やアクセス権限の管理体制の強化が必要です。VPN接続や限定公開設定を活用することで、社外からの侵入リスクも低減できます。
加えて、外部プラットフォームを使って研修動画を配信する場合には、そのサービスのセキュリティポリシーを事前に確認し、更新頻度やサポート体制を含めた評価が重要です。
動画内の素材や内容についても、著作権と個人情報保護の観点から配慮が必要です。映像・音声・画像のすべてにおいて、正当な権利があるかを確認し、必要に応じて社内でのレビューや法務部門のチェックを通すことで、リスクの未然防止につながります。
効果的な研修動画の作成方法
テーマ選定の重要性
効果的な研修動画を制作するうえで、最初にして最も重要なのがテーマの選定です。受講者にとって価値のある内容を提供するには、対象業務やスキルレベルに合った適切なテーマを設定する必要があります。ニーズに合致しないテーマでは、関心を引くことが難しく、学習効果も得にくくなります。
また、選定したテーマが企業のビジョンや戦略と整合していれば、研修内容が実務と直結しやすくなり、学んだ知識が現場での行動や成果に結びつきやすくなります。現場で抱える課題に寄り添ったテーマであれば、受講者の共感を得やすく、理解も深まりやすくなります。
さらに、研修動画のテーマは全体の構成や演出にも大きな影響を与えます。抽象的な説明に終始するのではなく、業務の具体的な事例やケーススタディを取り入れれば、視聴者にとって実践的で身近な内容に仕上がります。どのような切り口で伝えるかによって、動画の伝わり方も大きく変わるため、企画段階でテーマを慎重に見極め、目的とターゲットに沿った軸を定めることが研修動画の成功を左右します。
成功するコンテンツ制作の例
研修動画のコンテンツを効果的に仕上げるには、まずターゲット層の理解が欠かせません。視聴者の業務内容、スキルレベル、課題意識などを把握すれば、必要とされる情報を的確に届けられます。現場の実態に即した内容であれば、受講者の関心を引き、学習への意欲も高まります。
構成面では、情報をただ羅列するのではなく、ストーリー仕立てにすることで理解が深まります。たとえば、「問題提起 → 解決策の提示 → 実践への応用」といった流れをつくれば、視聴者が自然に学びに引き込まれます。
また、視覚的な表現にも工夫が求められます。グラフィックやアニメーションを使って情報を補足すれば、印象に残りやすく、理解の助けにもなります。インタラクティブな要素を取り入れると、受講者が自ら考え参加する姿勢が促され、学習の効果も高まります。
さらに、動画の長さにも配慮が必要です。長時間の動画は視聴者の負担になるので、長い場合は短いチャプターに分け、必要な部分だけを視聴しやすくすれば、利便性も高まります。
最後に、フィードバックをもとにした改善の仕組みを組み込むことが重要です。視聴者から得た意見を分析し、コンテンツの内容や構成を見直せば、次回以降の研修動画の質も向上します。このように、視聴者目線に立って制作と改善を重ねることが、効果的な研修動画づくりの鍵になります。
【〇✖比較表】付き! 生成AIと機械学習AI
AIチャットボットの違いがわかるガイド
研修動画の活用シーン
| 活用シーン | 主な目的 | 特徴・利点 |
| 新入社員研修 | 企業文化・業務理解 |
視覚で伝わりやすく、均質な教育が可能 |
| スキルアップ研修 | 実務能力の向上 |
自分のペースで繰り返し学習できる |
| コンプライアンス研修 | 法令・倫理の理解促進 |
実例やシナリオで行動変容につなげやすい |
新入社員研修
新入社員には、企業文化、業務プロセス、社内ルールなど幅広い情報を短期間で伝える必要があります。こうした情報を一斉に提供する場面でも、研修動画は非常に効果的です。図解や実写映像を組み合わせれば、視覚的に理解しやすくなり、言葉だけでは伝えにくい企業の雰囲気や現場の動きも直感的に伝えられます。
また、配属前のオンボーディングの段階から動画を活用することで、入社後の混乱や不安を軽減し、早期の戦力化にもつながります。字幕や多言語対応のナレーションを組み込めば、外国人社員への対応もスムーズになり、グローバル人材の受け入れにも柔軟に対応できます。
スキルアップ研修
社員の能力開発を目的としたスキルアップ研修においても、動画研修の柔軟性は大きなメリットです。業務の合間や空き時間に自分のペースで視聴でき、必要な部分を繰り返し確認することで理解が深まります。とくに、ツールの操作方法や営業トーク、顧客対応などの実務スキルは、動画による再現と解説との相性が良く、短時間でも高い学習効果が期待できます。
また、マイクロラーニング形式で内容を細かく分割すれば、集中力を保ちやすくなり、継続的な学習習慣の定着にもつながります。
コンプライアンス研修
法令遵守や企業倫理に関する教育では、単に情報を伝えるだけでなく、正しい判断と行動を促すことが重要です。研修動画を使えば、具体的なケーススタディを取り入れて、「この状況で自分ならどう行動するか」を考えさせる構成にすれば、受講者の自律的な思考を引き出せます。
また、動画なら全社員に一貫した内容を届けられるため、社内教育の標準化にも有効です。定期的な更新も容易で、法改正や社内規程の変更にも迅速に対応できる点は、動画研修ならではの利点です。
研修動画の効果測定
受講者のフィードバック
研修動画のクオリティを高めていくためには、受講者からのフィードバックを定期的に収集し、それをもとに改善を重ねる姿勢が不可欠です。どの部分が理解しづらかったのか、どの内容が役立ったのかといった具体的な意見は、次回以降の動画制作に向けた重要なヒントになります。
フィードバックの手段としては、オンラインアンケートやコメントフォームの活用が効果的です。選択式の項目に加えて自由記述欄を設けると、受講者の本音や気づきをより深く把握できます。とくに視聴直後に回答を促すことで、内容に対する率直で鮮明な反応を得やすくなります。
集まった意見は、動画の構成、尺(長さ)、難易度、演出などさまざまな観点からの見直しに役立ちます。改善サイクルを回すことで、研修動画の完成度は回を追うごとに向上し、学習効果と受講者満足度の両面で成果が期待できます。
学習成果の評価
動画研修を効果的な人材育成手段とするためには、学習成果の可視化が重要です。これは、受講者が知識やスキルをどの程度習得し、実際の業務に活かせるようになったかを把握するためのプロセスです。
評価方法にはさまざまな手段がありますが、以下のように分類できます:
学習成果の主な評価方法
| 評価手法 | 内容 | 特徴 |
| 理解度テスト |
選択式・記述式などで知識の習得を確認 |
即時評価が可能/デジタル化しやすい |
| 実技・操作チェック |
実際の業務に近い作業で成果を判定 |
実践力の有無を把握できる |
| グループディスカッション |
学習内容をもとに意見交換を実施 |
理解の深さ・応用力が浮き彫りになる |
| 行動変化の観察 |
業務上の行動が研修後に変化しているかを追跡 |
実運用での効果を測定できる |
これらの評価結果は、研修そのものの見直しだけでなく、受講者ごとのフォローアップにも活かせます。たとえば、理解度が低かった社員には補足動画や復習コンテンツを提供し、学び直しをサポートする体制を整えることが可能です。
また、評価の定期的な実施で、教育のPDCAサイクルを構築し、長期的なスキル定着や行動変容を継続的に追跡できます。数字や具体的なフィードバックが蓄積されれば、経営層への報告や教育投資の正当化にもつながります。
研修動画の今後の展望
テクノロジーの進化と研修動画の可能性
近年のAI技術の進化により、研修動画は単なる映像教材から、「個別最適化された学習体験」へと進化しつつあります。受講者ごとの視聴状況や理解度に合わせて最適な内容を提供したり、学習履歴を分析してフォローアップのヒントを示したりと、従来の一方向的な学習から、より柔軟でパーソナライズされた形へと変わり始めています。
また、AIは研修の「視聴体験そのもの」を改善する領域でも存在感を増しています。特に、すでに作成・運用されている研修動画の「使いやすさ」や「探しやすさ」を高めることは、多忙なビジネスパーソンにとって重要なポイントです。
Video Questor:AI活用による研修運用の最前線
こうした中で注目されているのが、Video Questor(ビデオクエスター)です。これは、研修動画を「作る」ためのツールではなく、すでに存在している動画を、より“見やすく”“活用しやすく”するためのAIツールです。たとえば、受講者が動画の中から知りたい情報をチャットで尋ねると、AIが該当部分を抽出し、関連するタイムコードや要点を提示します。これにより、必要な情報にすぐアクセスできるだけでなく、動画全体を見返さなくても効率的に学習できます。
主な特徴は以下の通りです:
| 機能 | 説明 |
| 動画内容のチャット質問応答 |
質問を入力すると、AIが該当箇所を特定して回答を返す |
| 自動要約・マニュアル生成 | 長時間の動画から要点を抽出し、文章として出力 |
| タイムコード付き検索 | 動画内の該当シーンへ即時ジャンプできるリンクを自動生成 |
| 多言語翻訳・字幕生成 | グローバル対応として、日本語以外の言語にも対応 |
このように、Video Questorは動画の「質」を問わず、誰にとっても使いやすい研修環境を実現できるツールです。動画がどれほど長くても、複雑でも、「探したい情報にすぐ届く」「聞きたいことにすぐ答えてくれる」という体験が、受講者の学習意欲と効率を高めてくれます。
研修動画の「活用環境」が差を生む時代へ
これからの人材育成においては、「どんな動画を作るか」と同じくらい、「どんな風に動画が使われるか」が成果を左右する重要な要素になりえます。
AIの力を借りて、受講者のストレスや手間を減らすことができれば、学習はもっと自然で、効果的なものになります。今後、研修動画は“ただの教材”ではなく、“個別最適化された学びのインフラ”へと進化していくでしょう。
その未来を支えるツールのひとつとして、Video Questorは多くの企業に新しい可能性を提供しています。
まとめ
研修動画は、今や企業にとって欠かせない人材育成の手段です。視覚的にわかりやすく、繰り返し視聴できる柔軟性は、従来の集合研修では実現が難しかった効率的かつ質の高い教育環境を可能にします。
テーマの選定から制作、活用方法、評価まで、適切なプロセスを踏めば、研修動画は単なる情報伝達を超えて、現場での行動変容を促す強力なツールになります。さらに、受講者からのフィードバックや成果の可視化を通じて、動画の内容を継続的に改善していくことが、学習効果の最大化につながります。
また、今後はAIや視聴支援ツールの進化によって、「動画を見る」だけではない、より主体的で効率的な学びのかたちが求められるようになるでしょう。たとえば、既存の動画をそのまま活かしながら、要点抽出や質問応答機能を付加するツール「Video Questor」のようなソリューションは、研修の質を高めながら制作負担を増やさない方法として注目されています。
研修の成果を高めたい、人材育成をもっと効果的に進めたいとお考えであれば、まずは研修動画の活用を見直し、自社に合った学びの仕組みを整えていくことから始めてみてはいかがでしょうか。
当サイトでは、AIチャットボット、生成AI、ChatGPT、動画活用に関するダウンロード資料をご用意しております。ご興味のある方はダウンロードいただき、資料をご活用ください。
【資料】生成AIと機械学習AI AIチャットボットの違いがわかるガイド【〇×比較表】
【資料】生成AI 基本の『き』
RAGも使えるAIチャットボットトライアル
公開日:2025年11月25日
SHARE

この記事の著者 NDIソリューションズ株式会社 マーケティング部
おすすめ記事