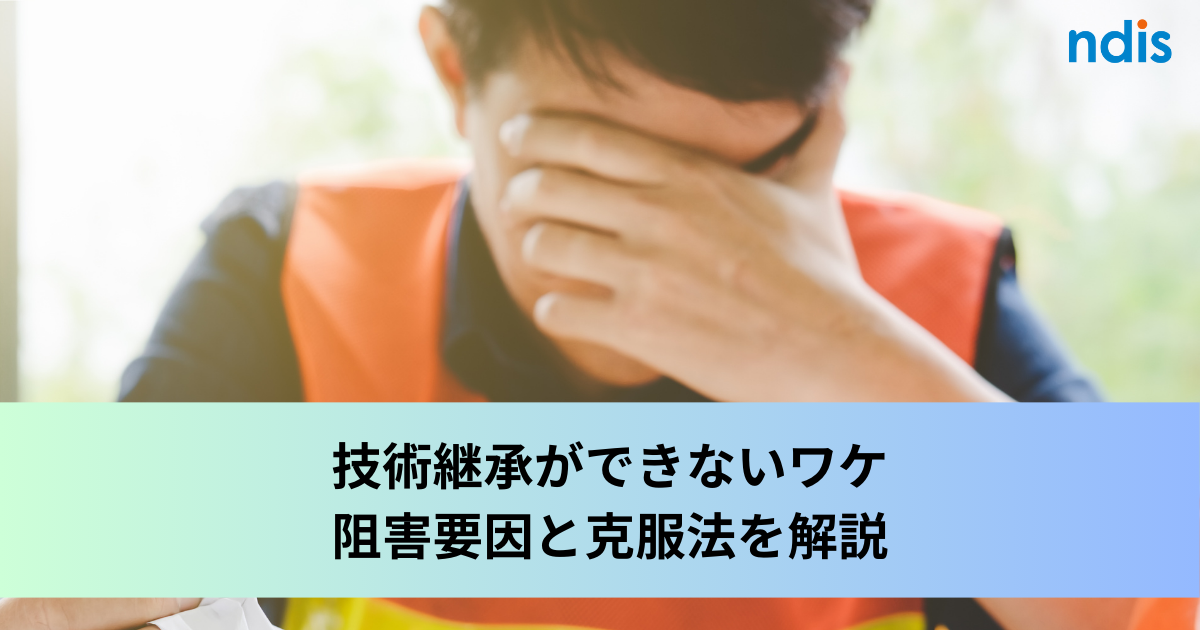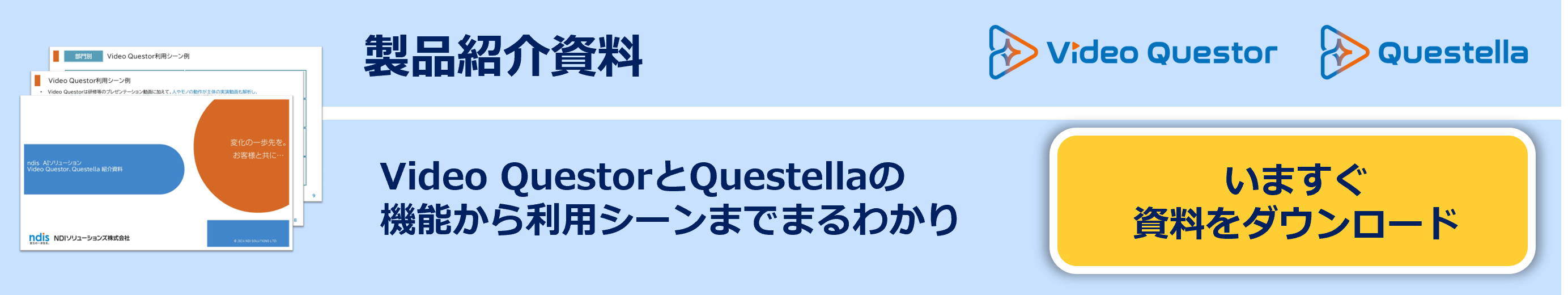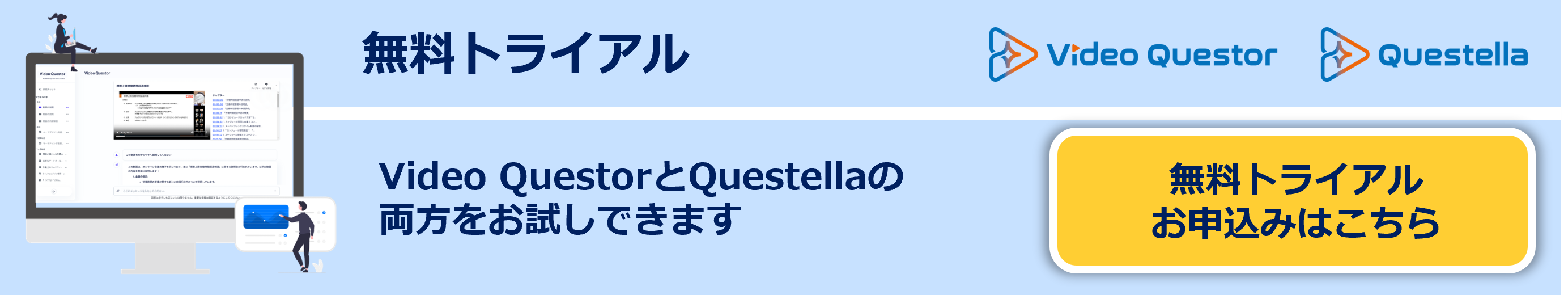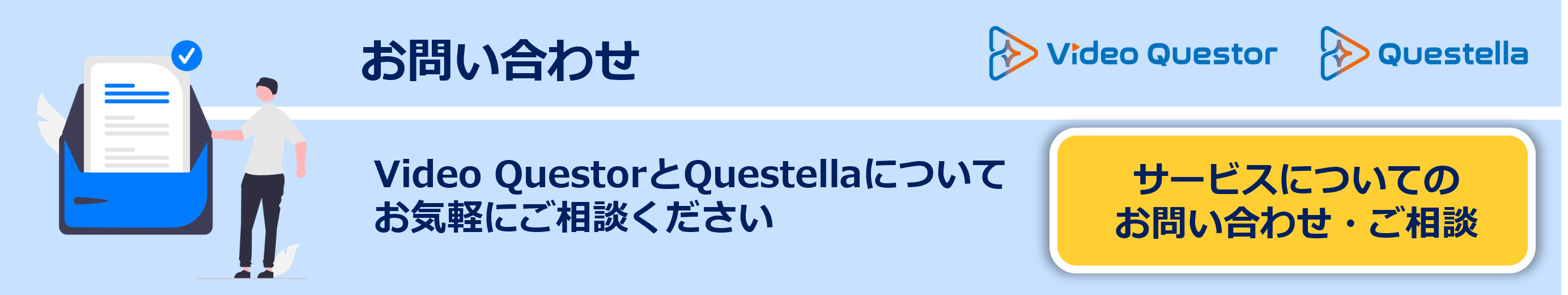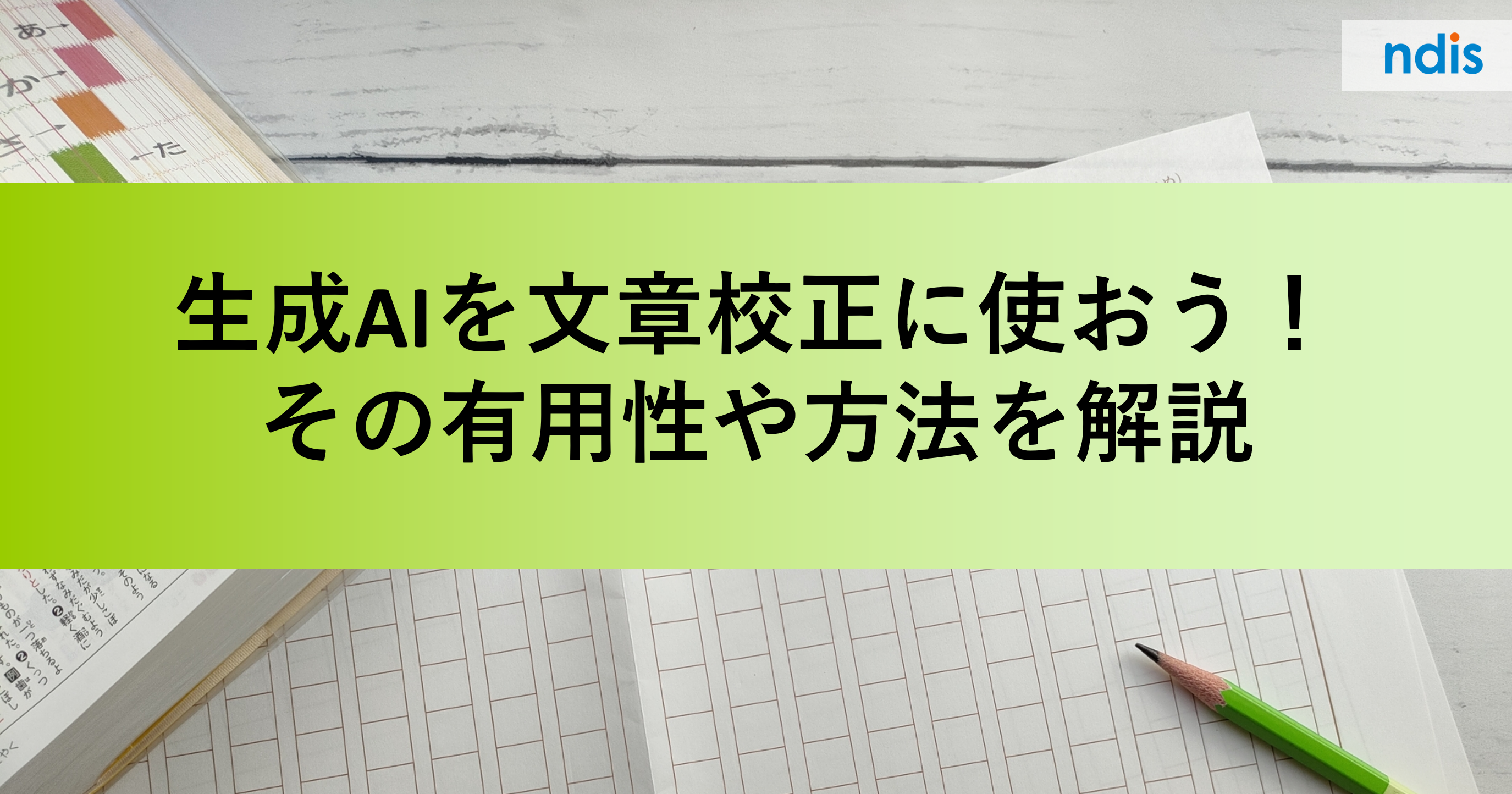無料生成AIに関する人気資料をまとめてダウンロードできます。
「技術継承できない」という課題は、今や多くの企業や組織で深刻な問題となっています。熟練技術者の退職や人材不足により、長年培われたノウハウが引き継がれず、業務の停滞や品質の低下を招くケースが増加しています。しかし、技術継承が進まない理由は単なる後継者不足にとどまりません。知識の属人化、教育システムの未整備、世代間の価値観やコミュニケーションの違いといった多くの要因が絡み合い、スムーズな継承を妨げています。
本記事では、技術継承がうまくいかない具体的な原因を分析し、企業が直面する課題を克服するための実践的な解決策を紹介します。特に、デジタル技術を活用した効率的な継承方法や、人材育成の仕組み作りに焦点を当て、持続可能な技術継承の実現に向けたステップを解説しました。
この記事を読めば、「なぜ技術継承ができないのか」「その問題をどう解決すればよいのか」が明確になり、今すぐ実践できる具体的なアクションプランが見えてくるはずです。
技術継承とは
最初に、技術継承の言葉の意味から確認しましょう。技術継承とは、企業や組織内で培われた技術やノウハウを次世代の従業員や後継者に伝えるプロセスを指します。これには、熟練した職人や技術者が持つ暗黙知を形式知に変換し、体系的に後進に伝えることが含まれます。技術継承の目的は、組織の競争力の維持と、持続可能な成長の実現です。特に製造業やサービス業などの現場では、個人の経験や勘に頼る部分が多く、これを形式化し、属人的な技術に頼らずに組織全体で共有できる知識に変えることが求められています。
特に認識すべき点として、技術継承は単なる情報伝達にとどまらず、企業文化や価値観の共有も含まれるため、単にマニュアルを作成するだけでは不十分だという点です。効果的な技術継承には、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)やメンタリング、ワークショップなどのほか、最近ではAIを効果的に使用した手法が活用されます。また、継承を成功させるためには、社内の在り方も変えていくのが大切です。ただ技術を機械的に伝えるのでなく、組織内のコミュニケーションの質を向上させ、信頼関係を築くことも非常に重要です。見落としがちな点ですので、覚えておきましょう。
技術継承は一度完了すれば良いというものではなく、常に改善と更新が求められます。技術は時代と共に進化し続けるため、継承された技術も時代に合わせた更新が必要です。技術継承のプロセスを効果的に構築すれば、企業の競争優位をもたらし、長期的な成功に貢献しますので、すぐにでも対策を打つことをおすすめします。
技術継承・技術承継・技術伝承の違い
技術継承と似た言葉に、技術承継、技術伝承があります。いずれも組織や個人が持つ知識や技能を次世代に引き継ぐプロセスを指しますが、それぞれに微妙な違いがあります。まず、技術継承とは、企業や組織において、特定のスキルやノウハウを持つ熟練者から若手や後継者に知識を体系的かつ継続的に伝えることを指します。
一方、技術承継は、より法的・制度的な側面を強調する用語で、特に会社の経営権や事業そのものを後継者に引き渡す際に用いられます。技術継承と比べ、組織全体の運営方針や財務面も含めた広範な要素が関与します。
技術伝承は、文化や伝統の中で培われた技術を後世に伝えることを目的とし、地域社会や職人などの個人レベルでの取り組みが主流です。技術継承と比較すると、伝統や文化的価値の保存に重きを置いている点が特徴です。
このように、技術継承は企業や組織において、技術承継は法的な事業引継ぎに、技術伝承は文化的な価値の保存にそれぞれ焦点を当てており、目的や対象領域が異なることが理解できます。
なぜ社会で技術継承が求められるのか?
現代社会において技術継承が重要視されている理由は、急速な技術革新とグローバル競争の激化にあります。特に日本では、少子高齢化による労働力不足が顕著であり、熟練工の退職が進む中で、技術の喪失が懸念されています。これにより、企業は持続的な成長を目指す上で、技術継承の必要性がますます高まっています。
一方、世界を見渡すと、アメリカやドイツなどの先進国においても、技術力の維持と競争力の強化が課題となっています。これらの国々では、産学連携やデジタルツールを活用した技術継承の取り組みが進められており、アメリカでは2024年に、防衛産業において「21世紀型の防衛産業エコシステム」の構築を掲げた、コスト・速さ・規模のバランスを重視した技術発展と継承に注力すると発表されました。
ドイツではイノベーションを生み出していく場として欧州最大イノベーションハブを設立するなど、テクノロジーと人知の融合について積極的に投資しています。
また、中国やインドなどの新興国では急速な経済成長に伴い、技術継承による産業基盤の強化が急務となっており、次のシリコンバレーの立ち位置を確保できるのではないかという政府による予測さえあります。
こうした世界の動向を踏まえると、日本においても、国内外のベストプラクティスを取り入れつつ、業界や企業の特性に応じた技術継承の仕組みを構築することが求められます。特に、デジタル技術を活用した効率的な継承方法や、多様な人材の活用を通じた新たな技術創出が鍵となるでしょう。技術継承は単なる知識の伝達に留まらず、企業の競争力を左右する重要な要素であり、持続可能な社会の実現に向けた重要な取り組みとして位置づけられています。
今さら聞けない基本用語とリスクを総まとめ
生成AI 基本の『き』
技術継承が特に求められる業界
技術継承が特に求められる業界としては、製造業、建設業、医療業界、そしてIT業界が挙げられます。これらの業界は長年培われてきた熟練の技術と専門知識に大きく依存しており、それらを次世代に伝えるのが不可欠となっています。それぞれの業界において、技術継承が必要とされる背景を詳しく見ていきましょう。
製造業界
製造業では、高度な加工技術や機械の操作技術が求められ、これらは単なる教科書やマニュアルでは伝えきれない職人技が多く含まれています。日本の製造業は高品質で知られており、その品質を支えているのは職人が持つ経験や感覚に基づく技術です。これらの技術を失うことは、企業の競争力だけでなく、日本全体の産業基盤にも影響を及ぼす恐れがあります。
建設業界
建設業においては、長年の経験に基づく構造物の設計や施工技術が重要です。特に、地震の多い日本では、耐震技術に関する高度な知識が求められます。これらの技術は人々の安全に直結しており、適切に継承されなければ、国全体の安全性に影響を与える可能性があります。
医療業界
医療業界では、医師や看護師が持つ臨床経験や手技が患者の命を左右します。医療現場での技術は、単なる知識ではなく、実際の経験に基づくものであり、若手医師に確実に伝えることが求められています。これは医療の質を維持し、患者の安全を確保するために必須です。
IT業界
IT業界では、技術の進化が非常に速く、新しいプログラミング言語やフレームワークの習得が求められる一方で、既存のシステムを維持管理するための知識も重要です。ベテランのIT技術者が持つシステムの深い理解や問題解決のノウハウを次世代に伝えることは、システムの安定性や企業のIT戦略に直結しています。さらに、リモートワークの導入が進む中でのコミュニケーションの減少も、技術継承を難しくしている要因の一つです。
これらの業界では技術者の高齢化が進んでおり、ベテラン技術者が引退する際に技術を失わないよう、早期から技術継承の仕組みを整えることが必要です。技術継承は、単に技術を伝えるだけでなく、企業や地域の文化を継続的に支える重要な役割を担っています。適切な技術継承が行われなければ、競争力の低下や安全性の欠如といったリスクが生じる可能性があるため、早急な対策が求められています。
技術継承ができない8つの阻害要因

技術継承が企業でうまくできない理由には、以下のようなものがあります。
1.知識の属人化
特定の個人に技術や知識が集中すると、退職や異動時にその知識が失われるリスクが発生します。これにより、業務の停滞や品質低下が懸念されます。対策として、技術のマニュアル作成や動画撮影、定期的なワークショップやトレーニングの実施が重要です。また、メンター制度を導入し、経験豊富な社員が若手に技術を継承する仕組みを整えることでリスクを軽減できます。
2.文書化の不足
技術やプロセスが十分に文書化されていないため、新しい従業員が学ぶのに時間がかかります。特に、これまでの経験によって出来るようになった技術の場合、暗黙知として蓄積されてしまったため言語化が難しくなりやすいです。こうした課題を解決するには、敢えて言語化するのでなく、動作などを動画に残しておくのも一つの工夫点として挙げられます。
3.教育・研修の不足
新しい従業員に対する適切な教育や研修が不足しているため、技術の習得が遅れます。さらに、従来の時間をかけたやり方では、モチベーションの低下や業務の停滞を引き起こし、結果として従業員の退職につながる恐れがあります。技術継承を円滑に進めるためには、効率的で効果的な研修といった観点から再構築するのも、現代社会で必要なアプローチでしょう。
4.コミュニケーションの欠如
技術継承ができない原因には、部門間や世代間のコミュニケーション不足があり、異なる価値観やスタイルが情報伝達を妨げるケースも少なくありません。また、交流不足で信頼関係が築かれていない場合や、技術継承の重要性が組織全体で認識されていないことも問題です。対策として、定期的な交流イベントやメンター制度の導入、技術の重要性を組織文化として位置づけるのが有効です。
5.モチベーションの低下
技術継承ができない背景には、ベテラン社員が教えることに対してモチベーションを持たない点や、組織としての技術共有の仕組みが不足している点が挙げられます。この問題に対処するためには、まずベテラン社員の指導に対するインセンティブを設定し、技術共有を促進する文化を醸成することが重要です。また、技術を体系的に記録し、共有するためのデジタルプラットフォームの導入も効果的です。
6.技術の進化と変化
技術継承が困難な背景には、技術の急速な進化、技術者の高齢化、若手人材の不足があります。特に技術の進化スピードは速くなるばかりですので、技術継承のプロセスをアジャイルにし、定期的に見直しと改善を行うほか、外部の専門家やコンサルタント導入などによる、積極的な最新情報の取り入れ体制を構築することが有効となります。
7.リソースの不足
技術継承ができない背景には、人材や時間の不足が挙げられます。対策として、継承プロセスの標準化やデジタルツールによる情報共有を積極的に行うことを推奨します。また、最近では手軽にさまざまな生成AIサービスが活用できるため、それらを利用し熟練者の作業をデータ化・整理して技術を継承すると、効率よくこの課題を解消できます。
8.継承プロセスの不明確さ
技術継承が滞る原因の一つは、プロセスの不明確さです。これにより、どのように進めればよいかが分からず、継承が止まってしまうケースが多く見られます。対策として、まずは技術継承のステップを文書化し、具体的な手順を定めるのが重要です。さらに、役割の設定も不可欠です。各担当者の役割を明確にし、誰がどの部分を責任を持って指導するのかをはっきりさせれば、継承のプロセスがスムーズになります。継承プロセスを可視化するためには、デジタルツールを活用して情報を体系的に管理し、進捗状況を常に確認できるようにすることも効果的です。
「技術継承できない」で悩む企業や組織の取り組み
近年、多くの企業や組織が技術継承の難しさに直面しています。ベテラン社員の退職や若手人材の不足により、重要な技術やノウハウが失われるリスクが高まっている一方で、日々試行錯誤される新たな取り組みに注目が集まっています。この章では、技術継承を円滑に進めるための具体的な取り組みや対策について見ていきましょう。
京都府のスマート農業
 出展:京都府ホームページ
出展:京都府ホームページ
京都府のスマート農業は、伝統的な農業の技術継承において新たな可能性を提供しています。高齢化や後継者不足といった課題を抱える中、スマート農業の導入は、農業の効率化と若手育成の新たな道を切り開いています。スマート農業とは、AIやロボット技術を駆使して農作業を自動化し、データを活用して生産性を向上させる取り組みです。これにより、熟練者に依存していた作業がデジタル化され、若手や新規参入者でも高度な農業技術を短期間で習得できる環境が整い始めています。
例えば、自動走行トラクターやドローンによる農薬散布技術は若い世代でも簡単に扱えるため、熟練農業者が持つ知識や技術を効果的に次の世代へ引き継ぐことが可能になりました。またICTを活用した農作業のデータ化は、経験に基づく勘や技術の属人化を防ぎ、農業の現場で必要とされる知識を標準化し、若手や新規参入者が参画しやすい環境整備に貢献しています。こうした技術の進化に対応するため、京都府では研修プログラムや技術支援を積極的に充実させている点もポイントでしょう。
さらに、スマート農業の普及目的は技術継承以外にもあり、テクノロジー導入によって重労働が軽減されるため、若者だけでなく女性農業者の積極的な参入も期待されています。このように、スマート農業は単なる技術導入に留まらず、農業界全体の技術継承の新しいモデルを創出し、持続可能な未来を築く上で重要な役割を果たすのです。
【参考】京都府「スマート農業技術の開発・実証プロジェクト」「京都府公式Youtubeチャンネル」
新人を効果的に育てる製造会社
製造業において、現場に業界未経験の新人が入社してくることが多いため、現場での育成は単に作業を教えるだけでなく、技術を深く理解し応用できる力を養うのが求められます。ここでは、大田区産業振興協会が注目した、経験豊富な職人から若手への技術継承が成功している事例について見てみましょう。この企業では、技術を継承するための方法論に偏るだけでなく、社員同士のコミュニケーションを創出するための努力も惜しみなくされています。
まずこの現場では、最初に現場未経験の新人には数多くの現場経験を積ませることが重要だという、社内共通理解が生まれているのが特徴です。具体的には、製造過程の一部を担当させ、実際の作業を通じて技術を学ばせます。その際、既存社員全員で新人を見守り、また失敗を恐れず挑戦できる環境を整えることが成長を促進する、と継承する側がしっかり理解している点が評価されています。
さらに、作業手順書や失敗事例集を活用し、効率的に知識を吸収できるようサポートもされている点であったり、動画教材を取り入れ視覚的に技術を理解しやすくする工夫も見られます。特に、熟練者の作業を撮影した動画は、具体的な技術の動きを詳細に学べる貴重な資源ですので、製造業における動画活用は非常に効果的な方法です。
技術継承に成功する企業ではこのように、実践と理論を融合させた育成プログラムが、新人の即戦力化を実現している特長が伺えますので、ぜひ参考にしてみましょう。
神戸市による若手社員の技術力向上
 出展:神戸市ホームページ
出展:神戸市ホームページ
神戸市は、団塊の世代の退職に伴い、若手職員への技術継承が急務となっています。これに対応するため、神戸市は職員技術研修所を設立し、若手社員の技術力向上を図っています。この施設では、土木や建築の基礎技術から最先端技術に至るまで、多岐にわたる実践的な研修が行われています。
特にAIやドローンといった最新技術の導入を積極的に進め、若手社員が現代の技術ニーズに対応できるよう育成したり、過去のプロジェクトや震災復興の経験を展示し、実際の工事の流れや課題を可視化したりすることで、若手職員の理解を深めています。
技術継承を単なる知識の伝達と考えるのではなく、若手職員が自ら考え行動できる環境を提供しています。今後は三宮再開発などの大規模プロジェクトも控えており、実地研修の充実化が期待されています。これらの取り組みを通じて、神戸市は持続可能な都市発展を支える技術力を備えた次世代のリーダーを育成し、地域社会の発展に寄与しているため、技術継承のモデルケースとして、全国の自治体にもその取り組みが注目されています。
【参考】神戸市「職員技術研修所での研修をスタートします」
「技術継承できない」を克服させる仕組み化とは?
技術継承がうまくいかない企業の多くは、「仕組み化」の欠如が原因となっています。属人化した知識が共有されず、ベテラン社員の退職とともに重要なノウハウが失われるケースも少なくありません。以下では企業内で技術継承を仕組み化する方法を解説し、その効果や具体的な実践例を紹介します。組織全体の生産性を向上させ、持続的な成長を実現するためのヒントが得られるでしょう。
企業内での仕組み化と期待効果
企業内での技術継承を効果的に行うためには、明確な仕組み化が不可欠です。仕組み化とは、技術や知識を体系的に整理し、組織内で誰もがアクセスできる状態を作る取り組みを指します。これにより、技術の属人化を防ぎ、誰でも均一な情報を取得できる環境が整います。
例えば技術マニュアルや手順書の整備、デジタルプラットフォームを用いたナレッジシェアリングの促進をすれば、ベテラン社員の退職による技術の喪失を防ぎ、若手社員へのスムーズな技術移行が十分に可能となるでしょう。また、AIやデータ解析ツールを活用すれば、技術の効率的な継承と新たな視点の導入が図られます。さらに、研修プログラムの一環として、実践的なトレーニングを組み込むことで、座学だけでは得られない体験的な学習が可能となります。
こうした仕組み化の効果は、技術の継承にとどまらず、企業全体の生産性や競争力の向上にも寄与します。特に、神戸市のように技術力向上を目的とした施設を設けることで、最新技術を活用した実践的な学習環境が提供され、若手社員の成長が促進されるだけでなく、最終的にこれらの取り組みが企業や組織の持続的な成長を支える基盤となるのです。
人的資源の最適化
技術継承を成功させるためには、人的資源の最適化が不可欠です。具体的には、個々の従業員が持つ知識やスキルを最大限に活用し、組織全体の生産性と効率を向上させることが求められます。まず、従業員の強みや専門性を把握し、それを活かす配置や役割を設定するのが重要です。例えば、ベテラン社員の豊富な経験を若手に伝えるためのメンター制度を導入することで、効果的な技術継承が実現できます。また、定期的なスキル評価とフィードバックを通じて、従業員の成長を促進し、技術の進化に対応できる柔軟な人材を育成することも重要です。
さらに、チーム内でのコミュニケーションを活性化させるための施策も人的資源の最適化に寄与します。例えば、定期的なミーティングやワークショップを通じて、知識の共有と問題解決の場を設ければ、個々のスキルが組織全体に還元されます。また、技術継承の阻害要因として挙げられるリソースの不足を補うために、外部からの専門家を招いてのトレーニングやワークショップを行うことも効果的です。
最後に、モチベーションの向上が人的資源の最適化には欠かせません。従業員が技術継承に対して積極的に取り組むためには、目標を明確にし、その達成に向けた具体的なステップを示すことが重要です。達成度に応じた報酬制度やキャリアパスの提示も、モチベーションを高める一助となります。これにより、組織全体が一丸となって技術継承に取り組む基盤が整い、持続可能な成長を実現できます。
それでも技術継承できない?まずは動画を撮ってみよう

「技術継承できない」と悩む企業にとって、まず取り組むべきは現場の作業を動画に記録することです。言葉だけでは伝えきれない熟練者の技やノウハウを、視覚的に残せば、より効率的な継承が可能です。以下では、動画を活用した技術継承のメリットや、AIを用いた解析ツールの活用によって属人化を防ぎ、持続的な成長を実現するためのヒントを解説します。
現場作業風景を動画にしてみよう
技術継承の課題に直面している企業が、最初の一歩として取り組むべきは、現場の動作を動画に記録することです。動画は、複雑な作業や手順を視覚的に伝える最も効果的な方法の一つであり、言葉だけでは伝えきれないニュアンスや細かな動作を正確にキャプチャできます。特に製造業や建設業といった業界では、熟練者の技術やノウハウを次世代に伝えるために、実際の作業を映像として残すのが重要です。
動画を撮影する際には、全体の流れだけでなく、細部に焦点を当てたクリップも撮影することで、より詳細な技術の伝達が可能になります。
撮影した動画の活用方法
撮影した動画を活用すれば、技術継承のプロセスを大幅に効率化できます。具体的な作業手順や熟練者の技術を動画に記録することで、視覚的に学ぶ機会を提供できるため、言葉では伝えにくい微細な動作やニュアンスを新しい世代に伝えるのが可能になります。さらに、動画の中身を自動解析ツールや、対話型AIを組み合わせたツールを使用することで、関係者が容易に情報を引き出せるようになります。
最近では動画の中身をAIが自動解析し、動画内の特定の動作についての質問に対して、AIが該当する部分を指摘したり、詳しく説明するのが可能になっています。さらに、こうした動画は、リモートでのトレーニングや研修にも活用でき、地理的制約を超えて技術を共有する手段としても有効です。動画を活用すれば、従来のマニュアルや口頭での説明では難しかった部分を補完し、技術継承の質を向上させることが期待できます。また、これらの動画は時が経つにつれて貴重な知識のアーカイブとしても役立ち、新たな技術者が参照するリソースとして機能します。撮影した動画を適切に活用することで、組織全体の技術力向上を促進し、長期的な成長をサポートできます。
自動で動画解析 | Video Questorとは
Video Questor(ビデオクエスター)とは、動画解析とAIによる対話機能を融合した革新的なサービスです。動画をアップロードするだけで、AIが自動的にその内容を解析し、視聴者が興味を持ちそうなポイントを抽出します。この技術は、特に技術継承が課題となる業界で大きな力を発揮します。例えば、製造業や建設業では、熟練した技術者の作業手順を動画で記録し、それをAIが解析することで、新人や他の社員が簡単に知識を吸収することも可能にになります。
さらに、Video Questorは解析結果を基に、チャット形式でユーザーの質問に答えることが可能です。これにより、従来の一方的な視聴だけでなく、双方向の学習体験が実現します。技術の属人化や文書化の不足といった問題も、動画とAIを組み合わせれば、より効率的に解決することが可能です。
また、技術の進化や変化に対応するためにも、動画を活用した継承プロセスの構築が欠かせません。Video Questorを利用すれば、最新の技術やノウハウを常に把握し、組織全体で共有することができます。これにより、リソースの不足やモチベーションの低下といった阻害要因を克服し、企業全体の技術力の底上げが可能になります。
Video Questorは、その柔軟な機能により、様々な業界での活用が期待されており、特に教育やカスタマーサポート、マーケティングなどの分野でもその効果を発揮しています。月額制の導入により、コスト管理も容易で、企業や組織が抱える技術継承の課題に対する強力なソリューションとなるでしょう。
詳しい内容についてはぜひ資料をご覧ください。以下から無料で取得可能です。
Video Questor 製品資料をもらう
まとめ
この記事を通じて、技術継承の重要性とその実現に向けた具体的な方法について解説しました。技術継承は、特に製造業や建設業のような専門知識が求められる業界において必須のプロセスですが、知識の属人化や文書化の不足といった多くの阻害要因が存在します。これらの課題を乗り越えるためには、体系的な教育プログラムやモチベーションの維持が重要であり、技術の進化に伴う変化にも対応していかなければなりません。
具体的な事例として、京都府のスマート農業や製造会社での新人教育、神戸市の若手社員育成の取り組みを紹介しました。これらの取り組みに共通するのは、技術継承をシステム化し、継続的に改善する姿勢です。さらに、技術継承が難しい場合には、現場の動作を動画で記録することが有効です。Video Questor(ビデオクエスター)のようなAIツールを活用することで、動画解析を自動化し、効率的な知識の共有が可能になります。
最終的に、技術継承は企業や組織の持続的な成長を支える基盤であり、適切なリソースの配分と明確なプロセスの確立が成功の鍵となります。今後も技術継承の重要性を理解し、実践的な手法の導入が求められます。各組織が独自の課題に応じた解決策を模索し、技術を次世代に引き継ぐことが、未来の成長に繋がるのです。
当サイトでは、AIチャットボット、生成AI、ChatGPT、動画活用に関するダウンロード資料をご用意しております。ご興味のある方はダウンロードいただき、資料をご活用ください。
【資料】生成AIと機械学習AI AIチャットボットの違いがわかるガイド【〇×比較表】
【資料】生成AI 基本の『き』
RAGも使えるAIチャットボットトライアル
また、NDIソリューションズが提供する「動画活用×生成AIツール Video Questor(ビデオクエスター)」は、組織全体でのナレッジシェアリングを促進するツールです。Video Questorは、動画の内容を自然言語で要約したり、特定のトピックに関する質問に回答したり、動画の該当部分をピックアップして提示することができます。これにより組織内で共有される研修や会議などの長い動画の中から必要な情報へ迅速にアクセスでき、時間を節約できます。
Video QuestorとQuestellaの詳細については、Video Questor製品サイトをご覧ください。30日間無料トライアルも受付中です。
公開日:2025年4月1日
SHARE

この記事の著者 内山 ゆり
おすすめ記事