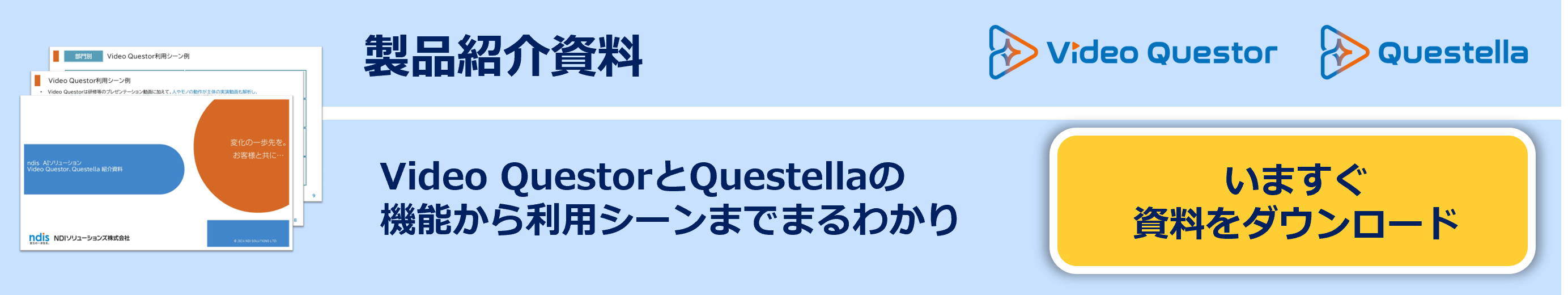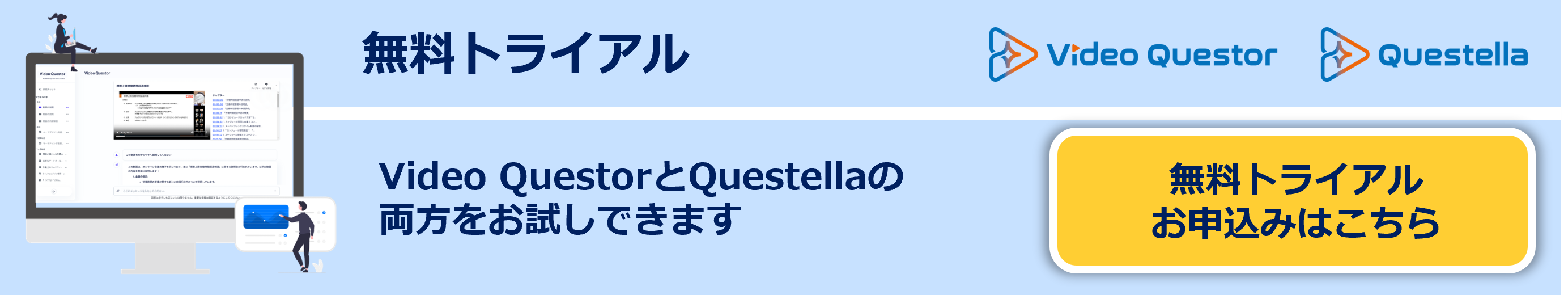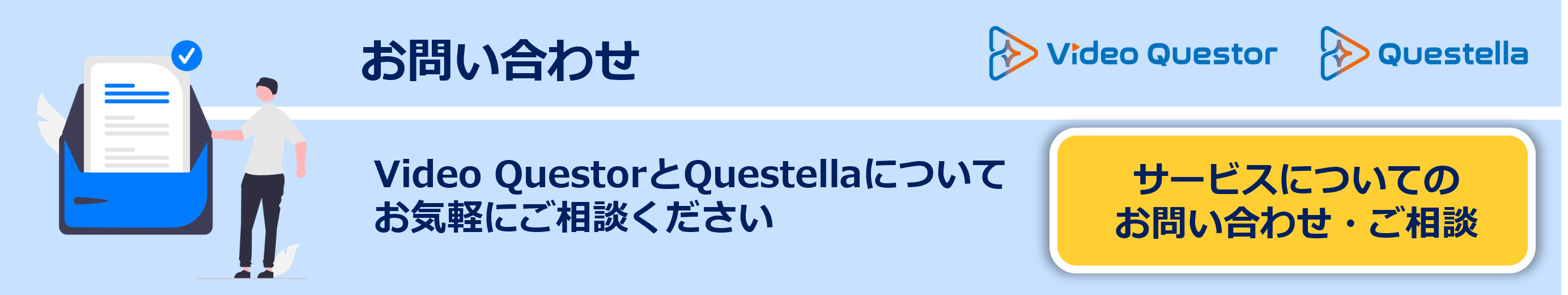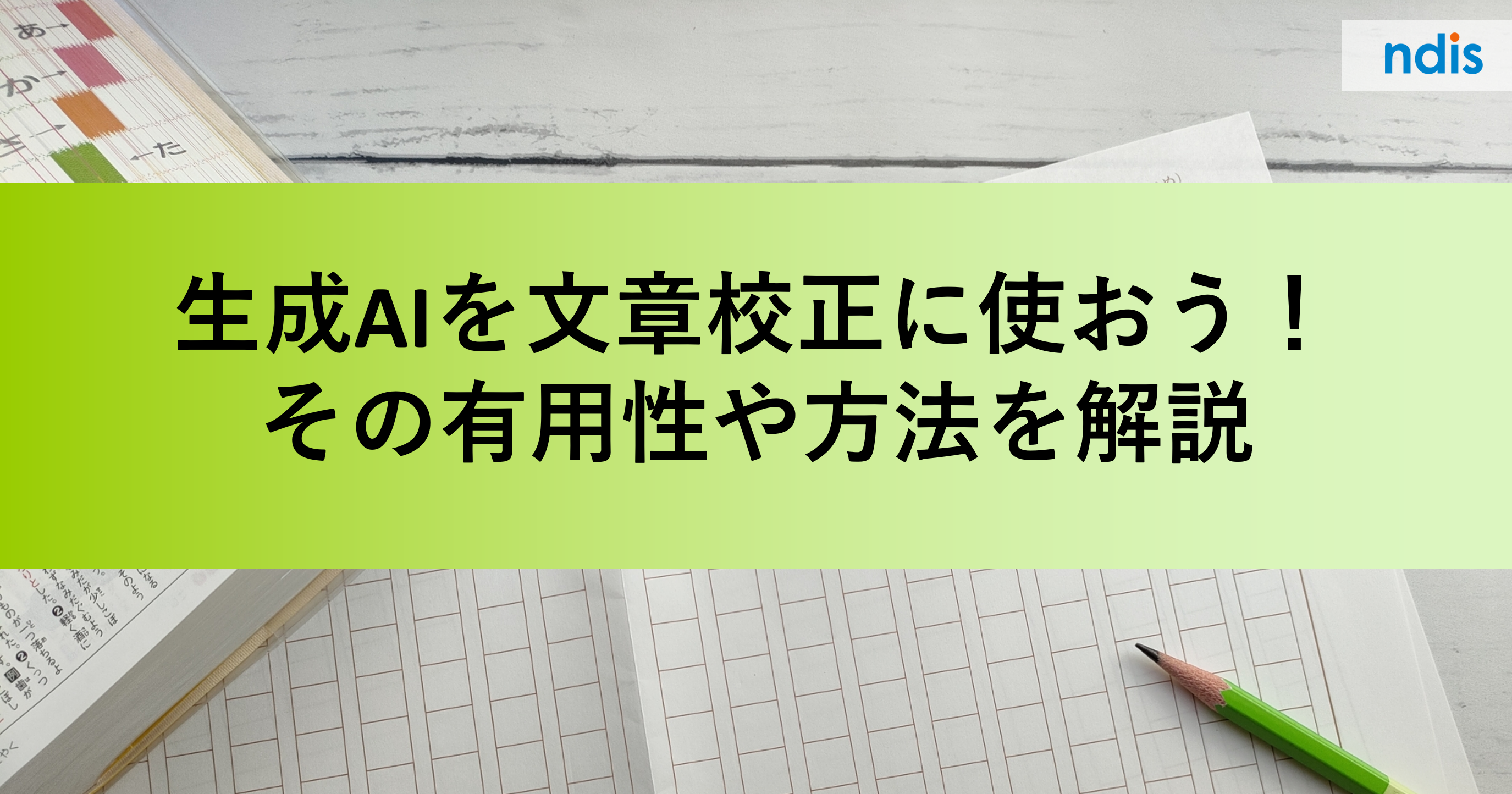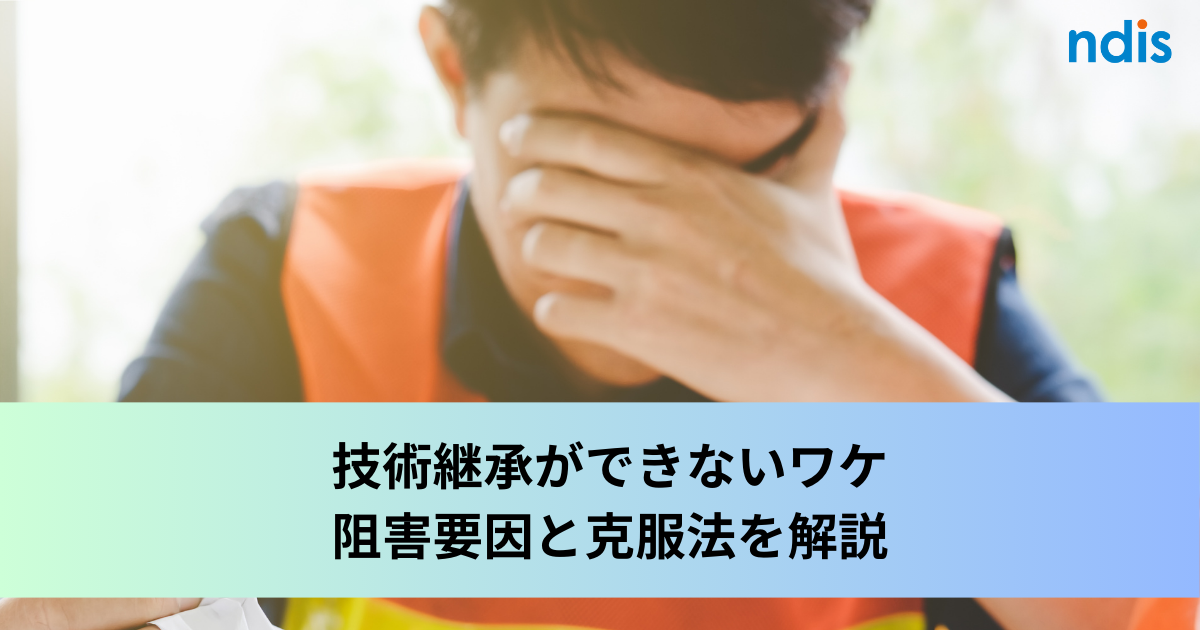無料生成AIに関する人気資料をまとめてダウンロードできます。
ビジネスシーンでよく耳にする「ナレッジ(Knowledge)」と「ノウハウ(Know-how)」。
どちらも“知識”を表す言葉ですが、実はこの2つには決定的な違いがあります。企業の人的資本にも関連するもので、情報と知識の活用は成功の鍵となりますが、その違いを明確に理解し、業務改善や情報共有にうまく活かしている企業は意外と多くありません。この違いを理解することができれば、業務改善や効率化に大いに役立ちます。
例えば、マニュアルは充実しているのに、現場では思ったように業務が進まない——。
属人化が解消されない、研修をしても成果に結びつかない——。
そうした悩みの背景には、ナレッジとノウハウの取り扱い方を間違えているケースが少なくないのです。
この記事では、言葉としては似ている「ナレッジ」と「ノウハウ」が、実際にはどう違い、どうすれば業務に活かせるのかを具体的に解説していきます。
さらに、ナレッジを組織で最大限に活用するための仕組みやツールについてもご紹介します。
- ノウハウとナレッジの違いとは?意味と使い分けを徹底解説
- ナレッジとノウハウの違いを活かした業務改善の考え方
- ノウハウとナレッジを活用するためのマネジメント手法と実践ポイント
- ナレッジマネジメントツールの選び方
- まとめ|ノウハウとナレッジを味方につけ、成果を最大化するには
ノウハウとナレッジの違いとは?意味と使い分けを徹底解説
ここでは「ナレッジ(Knowledge)」と「ノウハウ(Know-how)」の特徴を明らかにし、その違いを整理していきましょう。
ナレッジは「言葉で伝えられる」知識(形式知)
 ナレッジとは、言語化や文書化が可能な知識のことを指します。
ナレッジとは、言語化や文書化が可能な知識のことを指します。
マニュアルや業務フロー、FAQ、社内のナレッジベースなどに蓄積されている情報がその代表例です。
こうした知識は「形式知」とも呼ばれ、誰にでも共有しやすく、再利用が容易であることが特徴です。
例えば、マニュアルなどの業務手順書やレポート、教育資料などが形式知に該当します。
これらは組織内での知識の標準化を可能にし、新しいメンバーが短期間で業務を理解し、即戦力となるための重要な資源です。
ナレッジは、明示された情報であるため、組織の知識資産として蓄積されやすく、ナレッジマネジメントの基盤となります。また、形式知は、業務の改善や新製品の開発、問題解決の場面で活用され、イノベーションを促進する役割を果たします。
このようなナレッジ(形式知)の活用は、組織の効率性を高めるだけでなく、競争力を維持・向上させるために不可欠です。
さらに、ナレッジはデジタル化されることで、オンラインプラットフォームを通じて簡単にアクセス可能になり、組織全体の知識共有を促進します。デジタルツールを活用することで、ナレッジを効果的に管理し、組織の知的資本を最大限に活用することができます。
ここではナレッジの内容についてご紹介しました。次はナレッジと間違えやすいノウハウについてお伝えしていきます。
ノウハウは「体験を通して学ぶ」知識(暗黙知)
 ノウハウは経験や直感、勘などから得られる“体験的な知識”を指します。
ノウハウは経験や直感、勘などから得られる“体験的な知識”を指します。
ベテラン社員の判断基準、商談のタイミングの読み方、現場でのちょっとしたコツ……これらは文章にしにくい“肌感覚”のようなものです。
このような知識は「暗黙知」とも呼ばれ、言語化や文書化が難しく、マニュアルや書籍では完全に伝えきれない、経験に基づいた深い理解や技術の集合です。例えば、料理のレシピを見て作ることはできても、プロのシェフが持つような「感覚」を言葉で伝えるのはなかなか難しいです。こうしたノウハウ(暗黙知)は言葉では説明しきれない部分を補い、実践を重ねることで初めて体得できるものです。
このため、ノウハウは個人の経験やスキルに依存しやすく、組織内での共有が難しいという特徴があります。ノウハウを蓄積し、共有するためには、それを形式知に変換するプロセスが重要です。具体的には、体験を言語化し、動画や図解を用いて視覚的に共有するなどの方法があります。こうした努力により、ノウハウは単なる個人のスキルに留まらず、組織全体の財産として活用することができます。ノウハウの効果的な共有は、組織の知識基盤を強化し、新たなイノベーションを生む土台となります。
ナレッジとノウハウの違いは「言葉」か「体験」か
ここまでナレッジとノウハウについてそれぞれご説明しました。次に、ナレッジとノウハウの違いについてご紹介します。
ナレッジとノウハウの違いは、「ナレッジ=言葉で伝えられる知識」、「ノウハウ=体験でしか伝えられない知識」です。分かりやすく表でまとめました。
| 分類 | ナレッジ(形式知) | ノウハウ(暗黙知) |
| 特徴 | 言語化・マニュアル化が可能 | 言語化が難しく、感覚的 |
| 共有のしやすさ | 高い | 低い(属人化しやすい) |
| 活用シーン | 研修資料、業務手順書、FAQなど | 接客、交渉術、判断スキルなど |
| 組織課題 |
情報が陳腐化しやすい |
経験者の退職で失われやすい |
この違いをしっかり理解できれば、どの知識をどう管理・活用していくかの方針が見えてきます。ナレッジとノウハウは情報の性質と伝達方法が異なるため、業務改善においては両者を効果的に活用することが求められます。
したがって、ナレッジを基に業務の標準化を進める一方で、ノウハウの共有を通じて組織全体のスキル向上を図ることが重要です。特に、ノウハウを形式知化することができれば、より多くの人々にその価値を伝えることができ、組織の競争力を高めることに繋がります。
ナレッジとノウハウの違いを活かした業務改善の考え方
前章で見たように、「ナレッジ」と「ノウハウ」には本質的な違いがあります。この違いを理解したうえで、それぞれを適切に業務改善へ活かしていくことが、組織の生産性向上や属人化の解消につながります。
ここでは、業務改善を成功させるために実際のビジネスシーンにおける活用方法と考え方をご紹介します。
業務効率化におけるナレッジの活用ポイント
業務効率化を実現するためには、ナレッジの効果的な活用が不可欠です。ナレッジは形式知であり、文章化や共有がしやすいという特徴があります。そのため、「再現性の高い作業の標準化」や「業務手順の見える化」に最適です。
例えば、
- FAQの整備
- 手順書や業務マニュアルの作成
- 社内ナレッジベースへの蓄積
などが挙げられます。
ナレッジを可視化して誰もが容易にアクセスできる形で共有することで、属人性を排除し、誰でも同じ品質で業務を行える体制が整います。
また、新人教育のスピードアップや、情報のサイロ化防止、ナレッジ活用の価値を組織全体で共有することで、さらなる業務効率化を推進する土壌を整え、チーム全体の底上げに効果的です。
ノウハウ蓄積による属人化リスクの回避
言葉にしづらく、個人に依存してしまうことが多いノウハウは、業務の属人化を招き、組織全体の効率性を低下させるリスクを孕んでいます。
しかし、現場ではこのノウハウこそが、
- 問題解決の勘所
- 顧客との信頼関係構築
- ミスを防ぐ小さな工夫
といった、「成果を生むカギ」になっていることも少なくありません。
したがって、このノウハウをいかに引き出し、組織の資産にできるかが重要になります。
具体的には、
- 定期的なワークショップやフィードバック共有会
- ベテラン社員によるケーススタディの共有
- 動画での作業記録・解説
など、従業員同士で情報を共有し合う文化を醸成することと、「記録と言語化」を組み合わせることが有効的です。
また、ノウハウを共有する過程で、組織内のさまざまな視点やアイデアが交わることで、新たなイノベーションの創出も期待できます。
さらに、ノウハウの蓄積と共有を推進するためには、従業員のモチベーションを高める仕組みも重要です。例えば、知識共有への貢献度を評価し、インセンティブを提供する制度を整えることで、積極的な参加を促します。最終的には、組織全体でのノウハウ共有が常態化し、業務の属人化を防ぎ、持続可能な成長を支える基盤を確立することができるでしょう。
| 知識の種類/ 活用フェーズ |
(例)教育・研修 | 業務改善 | 標準化・仕組み化 |
| ナレッジ (形式知) |
|
|
|
| ノウハウ (暗黙知) |
|
|
|
両者を組み合わせたナレッジマネジメントの進め方
最も重要なのは、「ナレッジ」と「ノウハウ」を“別物”として扱うのではなく、“補完関係”にあるものとして設計することです。
- ナレッジで「基本を標準化」し、再現性を高める
- ノウハウで「現場の工夫や判断力」を共有し、柔軟性を持たせる
この両軸をバランス良く取り入れることで、ただのマニュアル主義にも、属人依存にもならない強い組織ができあがります。
そして今、こうしたナレッジマネジメントを支援するツールや仕組みが、注目されています。ナレッジマネジメントは一度確立したら終わりではなく、常に進化し続けるものであるため、PDCAサイクルを回しながら、組織のニーズに応じた柔軟な対応が求められます。これにより、組織全体の知識資産を最大限に活用し、業務効率化や企業競争力の向上を実現できます。
今さら聞けない基本用語とリスクを総まとめ
生成AI 基本の『き』
ノウハウとナレッジを活用するためのマネジメント手法と実践ポイント
ノウハウとナレッジの効果的な活用には、適切なマネジメント手法の導入が不可欠です。このマネジメント手法をナレッジマネジメントと言ったりすることもあります。ここでは、ナレッジマネジメントの基本的な考え方と、実践のポイントをご紹介します。
ナレッジマネジメントの基本と導入5ステップ
ナレッジマネジメントとは、組織内の知識(形式知・暗黙知)を収集・整理・共有し、価値に変える取り組みのことです。
ナレッジマネジメントを導入する際の流れについて5ステップでご紹介します。
- 知識の棚卸し(取得)
まずは、組織内にどんなナレッジやノウハウが存在するかを洗い出します。 - 重要知識の選別(整理)
業務に直結し、共有することで価値が高まる知識を明確にします。 - 形式知化と保存(保存)
ナレッジはマニュアル、FAQ、ナレッジベースなどに蓄積しやすい形で保存します。
ノウハウは形式知化した後に、ナレッジベースなどに蓄積します。
※ノウハウを形式知化する工夫は次の章で詳しく紹介します。 - 共有・活用の仕組みづくり(共有)
社内ポータルやツールを活用し、誰でも必要なときにアクセスできる環境を整えます。 - 継続的な更新と改善(更新)
知識は陳腐化しやすいため、定期的なレビューとアップデートが欠かせません。
ナレッジマネジメントは、導入して終わりではなく、運用し続けて組織の“学習力”にすること、言い換えると、得られた知識を活用し、新しいアイデアの創出やイノベーションを推進することがゴールです。導入後は、定期的にその効果を測定し、必要に応じてプロセスを見直すことで、持続可能な知識管理体制を構築できるでしょう。
ノウハウを形式知化するための社内の仕組み作り

暗黙知であるノウハウを形式知に変えるには、工夫と仕組みが必要です。
例えば:
- OJTで気づいたことをその場で記録する文化をつくる
- 動画で熟練者の動作や会話を記録し、あとから解説を加える
- 「この仕事のコツ」などの短文投稿をナレッジベースに集約
こうした小さな工夫の積み重ねが、やがて大きな知識資産になります。
ノウハウの形式知化に成功すれば、新人でもベテランの感覚を学べる環境が整い、教育コストの削減や早期戦力化につながります。
また、ノウハウを形式知化するための社内の仕組み作りは、企業において重要な課題となるでしょう。情報共有を促進する文化とルールのつくりのために、「知識を出し惜しみしない文化」の醸成も効果的です。
そのためには、
- 成果を出したノウハウを称賛する風土づくり
- 共有することが評価につながる仕組みの導入
- 書く/話すことが苦手な人でもアウトプットしやすいツールの採用
などの心理的・制度的なサポートが効果的です。
また、「ナレッジ共有=めんどうな仕事」という印象を払拭するために、投稿のしやすさや検索のしやすさも重要です。
こうした部分で、後述したようなナレッジマネジメントツールの活用が非常に効果を発揮します。さらに、形式知化を促進するために、社内教育やトレーニングプログラムを充実させることも重要です。ただし、教育や研修を「やりっぱなし」「受けっぱなし」にするだけでは、ノウハウの定着や活用にはつながりません。
そこで有効なのが、学びの場に「双方向のコミュニケーション」を取り入れることです。
例えば、
- 受講後にすぐ質問できるチャットスペースを設ける
- 研修動画に対してリアルタイムで質疑応答ができる環境を整える
こういった環境が整っていれば、理解を深め、実践に結びつきやすくなります。
また、質問や疑問を誰でも気軽に投げかけられる「聞きやすい空気感」や、「聞いたことに対してきちんとフィードバックが返ってくる」安心感も非常に重要です。
こうしたオープンな知識循環の仕組みが、形式知化したノウハウの定着を後押しし、自発的な共有を促進します。
さらに、質問と回答の履歴をナレッジベースに蓄積すれば、後から同じ疑問を持つ人の助けにもなり、組織全体で知識の再利用が可能になります。
このように、「教える⇄学ぶ」だけでなく、「聞く⇄答える」「蓄積する⇄活用する」といった知識の循環構造をつくることが、ノウハウの形式知化とナレッジマネジメントを成功させる鍵となるのです。
ナレッジマネジメントツールの選び方
ナレッジやノウハウを組織内で共有・活用していくためには、人の意識改革や仕組み作りとともに、それを支えるツールの導入が欠かせません。
特に、情報の集約、検索性の高さ、ユーザー間のコラボレーションを効率的に行えるツールは、ナレッジマネジメントの実践において非常に強力な武器となります。ナレッジマネジメントツールにはさまざまな種類がありますが、業務効率化や属人化の解消において特に重要なのは、次のような機能です。
|
このような機能を備えたツールを導入することで、知識の共有・活用のハードルを大きく下げることができます。
おすすめのナレッジマネジメントツール3選|特徴と使い分けポイント
ナレッジマネジメントツールには、それぞれ得意領域や向いている業務シーンがあります。以下では、人気の3製品について「特徴・主な機能」と「どんな企業におすすめか」「他では補えないポイント」までをわかりやすく比較しました。
1.Qast(any株式会社) https://qast.jp/
◆特徴
- Q&A+Wiki形式で組織に埋もれる個人の知識や経験を引き出すナレッジプラットフォーム
- 日常的な“質問と答え”をナレッジ化できる社内の「知恵の掲示板」
- Slack/Teamsと連携し、社内コミュニケーションの延長で使える点が好評
◆主な機能
- Q&A機能、社内Wiki、コンテンツ共有、タグ付与、自動要約、類似投稿サジェスト、マニュアル作成・編集機能
👤 おすすめユーザー像
- 日々の業務で「これどうするの?」が多発する企業
- 部署間の情報共有を促進したい企業
- 社内の“質問しやすい空気”を活かしたい方
2. NotePM(株式会社プロジェクト・モード) https://notepm.jp/
◆特徴
- 社内版ウィキペディアとして、情報を効率的に管理できるナレッジ共有ツール
- マニュアル・業務手順書の整備に強く、社内の「ナレッジ図書館」として活躍
- 階層フォルダとテンプレートで体系的に管理しやすい
◆主な機能
高機能エディタによる文書作成、情報共有、ナレッジ共有、無料トライアル後の運用サポートやコンサルティング
👤 おすすめユーザー像
- 開発ノウハウや技術情報を効率的に管理したい企業、ものづくりが好きな方
- ドキュメントでしっかり整備したい企業
- マニュアルや業務フローを社内標準として定着させたい方
3. Video Questor(NDIソリューションズ株式会社)https://solution.ndisol.jp/videoquestor
◆特徴
- AIが動画を解析し、チャット形式で質問に対応する動画ナレッジ特化型ツール
- チャット指示により、AIが情報を抽出・要約
- 研修・会議・OJT動画の共有や検索、FAQ対応まで非常に効率的に行える
◆主な機能
- 動画アップロードで内容解析、チャット指示で文章生成や質問回答・要約、翻訳、マニュアル作成
👤 おすすめユーザー像
- 動画コンテンツを深く理解し、業務効率を向上させたい企業。
- OJT中心で“現場の感覚”を伝える機会が多い現場
- 属人化を解消し、暗黙知をチームに広げたいマネージャー層
✅ Video Questorの優位点
Video Questorは、動画からノウハウを抽出し、実践的な現場知を共有できる強力なツールです。このツールを使えば、動画の中身を自動で検索・要約し、実務に直結した知識活用が可能となります。また、暗黙知の見える化、実践知の共有、動画検索のスピードが圧倒的に高い点も魅力です。
他のツールでは共有しきれない体験的ノウハウ(暗黙知)を、動画ベースで形式知化できるのがVideo Questorの最大の強みです。長尺動画から"使える情報"だけをピックアップすることで、動画の内容を確認する時間を大幅に短縮することができます。さらに、ノウハウ共有が「自然に、いつでも、誰にでも」できる環境づくりを強力にサポートします。
Video Questorの優位点は、動画を活用して知識を共有することにあり、従来のテキストベースのナレッジ管理ではカバーしきれない視覚的で直感的な情報伝達を可能にするという点です。研修や会議、OJT動画の共有や検索、FAQ対応まで非常に効率的に行えることが特長です。
| ツール名 | こんな人・組織におすすめ | 得意なナレッジ領域 | 苦手なナレッジ領域 |
| Qast |
|
|
|
| NotePM |
|
|
|
| Video Questor |
|
|
|
まとめ|ノウハウとナレッジを味方につけ、成果を最大化するには
「Video Questo「ノウハウ」と「ナレッジ」は、どちらもビジネスの成果を左右する重要な知識資源です。
しかし、それぞれの性質や扱い方を理解しないままでは、せっかくの知識も組織全体に活かしきれません。
ナレッジ(形式知)は、言語化・共有がしやすく、業務の標準化や教育効率の向上に貢献します。
一方で、ノウハウ(暗黙知)は、現場で得られる貴重な経験則であり、差別化や判断力の源となります。
ノウハウとナレッジを活かしたマネジメントは、組織の成長や生産性向上に欠かせない要素です。この2つを適切に切り分けて管理し、必要な知識を、必要な人に、必要なタイミングで届けられる仕組みを整えること。それが、ナレッジマネジメントの本質であり、企業の成長を支える基盤になります。
当サイトでは、AIチャットボット、生成AI、ChatGPT、動画活用に関するダウンロード資料をご用意しております。ご興味のある方はダウンロードいただき、資料をご活用ください。
【資料】生成AIと機械学習AI AIチャットボットの違いがわかるガイド【〇×比較表】
【資料】生成AI 基本の『き』
RAGも使えるAIチャットボットトライアル
また、NDIソリューションズが提供する「動画活用×生成AIツール Video Questor(ビデオクエスター)」は、組織全体でのナレッジシェアリングを促進するツールです。Video Questorは、動画の内容を自然言語で要約したり、特定のトピックに関する質問に回答したり、動画の該当部分をピックアップして提示することができます。これにより組織内で共有される研修や会議などの長い動画の中から必要な情報へ迅速にアクセスでき、時間を節約できます。
公開日:2025年7月17日
SHARE

この記事の著者 NDIソリューションズ株式会社 マーケティング部
おすすめ記事